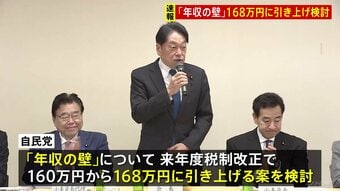■すり込まれた男女の役割 解消への道は?
ーー杉山さんが10代、20代のころは、まだジェンダー格差への意識が高まっていなかったはずですよね。今はもうそこまでひどくはないと願います。
そうですね。でも、時代は変わっても、もしかしたら自分の中にもアンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)があるかもしれないと常に意識することが大切だと思います。以前、付き合って数年たったころ、僕のパートナー(女性)が友達の結婚式で韓国に行く機会がありました。別に僕にそんなお金があるわけでもなかったんですが、せっかく行くなら、何か向こうで美味しいもの食べておいでよってお金を渡したんです。そしたらパートナーにすごく怒られました。彼女からすると、馬鹿にされたという感じがしたのかもしれません。
実は、僕は典型的な性別役割分業がはっきりした家で育ちました。父は外で仕事、母が家事育児する専業主婦で、僕もあんまりそういったことに疑問を抱かずに来てしまっていました。お父さんが稼いで、家族を養う。母が出かけるときには父がお金を手渡す、そんな当たり前のように見てきた光景から刷り込まれた、まさにアンコンシャス・バイアスです。社会的マイノリティの当事者だからといって、偏見がないわけではありません。今改めて考えてみると、母だってきっと仕事したらめちゃくちゃ仕事できる人だったんだろうなと思います。
一方で、親父世代は、子育てに関わりたいと思ってもできなかったとも思うんです。子どもが生まれたからという理由で大事な接待を断ったら、「お前仕事なめてんのか」みたいな時代だったと思います。いま僕は男性ジェンダーでありながらも、かなりの時間を子育てについやしていますが、仕事とか他の人間関係では得られないような貴重な経験をしてると感じ、毎日が本当に充実しています。でも僕も時代が違えば、うちの父のように子どものオムツなんか替えたことないと言ってたかもしれません。もし子育てに関われないまま過ごしてしまっていたら、なんてもったいないことしたんだろうと思うんです。だから、これは個人のせいというよりも、時代や社会のあり方次第なのかなとは思っていて、個人を責めるようなものではないなとも思います。
ーー“女性”と“男性”の間を隔てる壁を崩すには何が必要だと感じていますか?
これが一番難しいんですけど、やっぱり自分の特権に気づいて、弱い立場のほうに意識的に寄り添うっていうことしかないと思うんですよね。よくLGBTQの話でもあるんですが、例えば同性婚というと、「なんであいつらばっかり特別扱いするんだよ」っていう話になることがあります。でも見方を変えて、何で結婚できる人たちが、できない人たちに「すべきじゃない」と言えるのか、と考えられないでしょうか?「特別扱いしている」のではなく、多くの人が“結婚できる”という特権を持っていて、結婚による恩恵を受けられる有利な立場にあるということは、当たり前にその権利がある人はなかなか気づけないわけです。
じゃあ、どうするのかというと、僕が最近よく例えてるのが公園にあるシーソーです。すごく重たい人と、すごく軽い人がシーソーに乗っていて、不均衡になっている。シーソーを平らにしたいなと思ったときに、どこに乗るべきでしょうか?「僕は中立な立場なんで」と、よかれと思って真ん中に乗ってしまってはいないでしょうか? 真ん中に乗っちゃうと、シーソーの傾きは結局変わらないです。中立は強い立場にさらに加担してしまいます。平等を目指すなら、勇気を持って軽い方に、つまり立場の弱い人の方にあえて寄り添って乗ることで、傾きがしっかりと戻っていくと思います。社会の仕組みは、まだまだ男性優位に作られてしまっている現実、その不均衡に気づいて、あえて女性に機会を増やしたり、支援をしていくことが必要だと感じています。
杉山文野:
1981年東京都生まれ。フェンシング元女子日本代表。トランスジェンダー 早稲田大学大学院修了。日本最大級のLGBTQ啓発イベントを運営するNPO法人東京レインボープライド共同代表理事や、日本初となる渋谷区・同性パートナーシップ制度制定に関わる。 2021年6月から日本フェンシング協会理事、日本オリンピック委員会(JOC)理事に就任。現在は2児の父として子育てにも奮闘中。著書に「元女子高生、パパになる」(文藝春秋)、「3人で親になってみた ママとパパ、ときどきゴンちゃん」(毎日新聞出版)など。