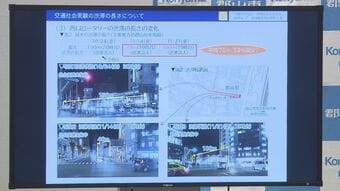過酷な“冬の活動”想定
去年の元日に起きた、能登半島地震。この時、いち早く被災地での対応にあたったのが、災害派遣医療チーム=DMATです。ひとたび災害が起きれば、すぐに派遣されることが多いDMATですが、普段も災害に備えた訓練を続けています。

5月24日。福島県いわき市の常磐病院で、DMATによる訓練が行われました。
看護師・大垣竜一郎さん「野宿もできる装備を揃えなきゃと思って、今回揃えたので、積み込みと実際の展開訓練をやってみようと」
医師や看護師のほか、医薬品の調達などを担当する業務調整員の5人1組で構成されるDMAT。常磐病院では、2年前に発足し、能登半島地震の被災地にも、派遣されました。この日は、災害の発生を想定し、準備した物品を積み込んで、現場で展開するまでを確認します。

向かったのは、いわき市内にある隊員の自宅です。時間との戦いともなる被災地での活動。要請を受けた後、スムーズに出動し、実際の活動に迅速に移ることができるのかも大切になります。5月の訓練でしたが、この日は冬の活動を想定しました。その理由は、寒さに備えた装備のほか、テントやカセットコンロなど、準備する物が最も多くなるのが、冬の活動となるためです。

能登半島地震で派遣された隊員たちは、被災地の過酷な環境を次のように振り返ります。
看護師・大垣竜一郎さん「能登で派遣されたときは寝具が毛布しかなくて、硬いコンクリートの床に毛布を敷いて1枚のスペースで男二人で寝る過酷な状況だった」