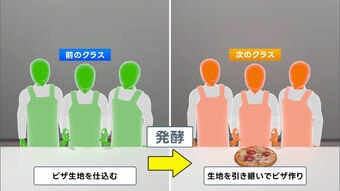無差別爆撃の悲惨さ

福岡大空襲で焼けた地域は、どのくらいの広さがあったのでしょうか。福岡市には、博多港と福岡港が埠頭を挟んであります。焼けた地域は2つの港の海岸線沿い。東は櫛田神社(博多区)、西の大濠公園(中央区)から北側、海岸線までの幅1.8キロメートルがほぼ焼失しています。たった2時間の空襲で死者902人、負傷者1,078人、行方不明244人。
※福岡市では、中心部のほか、春吉、高宮、住吉、堅粕、三宅、花畑、柏原、清水、千代、東住吉、曲淵、内野、東入部、田熊、有田、拾六町、福重、上山門、城原、内浜、今宿などが被災。糸島市香力・蔵持、那珂川市安徳なども被害が出ました。
先ほどお話ししたイランでは、13日以降に224人が死亡したと言います。イランでは防空システムをすり抜けたミサイルが着弾し、人が亡くなっているわけですが、防空態勢が事実上機能していなかった当時の日本で、200機超の大編隊。「じゅうたん爆撃」という言葉があります。全てを覆い尽くすように焼夷弾を落としていく。焼夷弾は、中に粘着質の油が入っています。重いので、当たったら人は即死します。家に当たると、屋根を突き破って部屋の中で油をばらまいて燃え出すので、消しようがありません。当時の日本には防空法があり、空襲時には逃げずに消火するのが国民の義務と定められていましたから、被害者は非常に多くなっていきました。
そこに、米軍による「無差別爆撃」が起きたわけです。日本軍で言うと、中国の戦時首都・重慶を1938年から6年間ずっと空爆を続け、5万人以上の死者を出しています。前年の1937年、スペインのゲルニカでナチスの爆撃が起きたのが、無差別爆撃の初めての例です。民間人の死者が出ることを厭わない。
ゲルニカがあり、その後日本による重慶。そして今度は日本が攻撃の対象となり、福岡だけでなく、日本の主要都市のほとんどがじゅうたん爆撃を受けていきます。民間人も含めた、非常に悲惨な殺傷ですが、東京裁判では重慶爆撃は戦犯追及の対象にはなっていません。連合国軍側も日本で同じことをやっていたからです。
フィールドワークで実感する軍事遺跡
6月14日(土)には、市民団体「ふくおか自由学校」が主催したフィールドワークがありました。元福岡市立高校の社会科教諭、江浜明徳さん(74歳)が案内してくれました。江浜さんは戦争遺跡の調査・研究をライフワークとしています。著書に『九州の戦争遺跡』(海鳥社)があり、防空壕や砲台跡など九州7県の84カ所を網羅している貴重な資料集を作っています。この日も圓應寺から、裏の供養塔に回ってみました。供養塔の横は、レンガ塀を挟んで旧簀子小学校の跡地です。

江浜明徳さん:ここで亡くなった方の数は176人。福岡市内の全犠牲者の2割に達します。簀子小学校が遺体の安置所。コンクリートで造られていたので、焼けなかったのです。たくさんのご遺体がここに運び込まれた。このレンガ塀は、圓應寺さんと小学校の境。小学校の中に安置されたご遺体は、この圓應寺側に運ばれ、火葬されたんだそうです。レンガ塀で、コンクリートで固めている場所があります。実は、「ここは遺体を搬出する通路になった」とご住職は言っておられました。よく見ると分かると思いますが、戦災の際にレンガが焼けた部分も黒く残っています。
江浜さんの案内があるとよく分かると感じました。176人の死者のうち、小学生が24人いたと言われています。再開発で今は変わっていますが、「ここがそういう場所だったのか」と、リアルに感じられました。供養塔の2メートル前で、ご遺体を焼いたのだそうです。近くでは子どもたちが遊んでいて、80年前との落差に驚かされました。