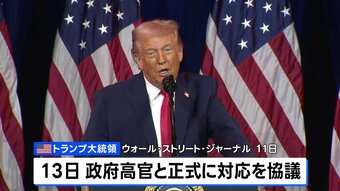「令和の米騒動」と呼ばれる今、コメに関するニュースを見ない日はありません。
政府が「備蓄米」を放出し、随意契約で売る事態に発展すると、スーパーには長蛇の列ができ、「支援者がたくさん米をくださるので、売るほどあります」などと発言した農水大臣は、消費者からの反感を買って辞任に追い込まれました。
お米の問題はなぜここまで、日本人の琴線に触れるのか。
『稲の大東亜共栄圏』といった著作があり、食と農業の歴史についてくわしい京都大学の藤原辰史教授に「米と愛国」というテーマで聞きました。
(TBSラジオ「荻上チキ・Session」2025年6月9日放送分から抜粋、構成=菅谷優駿)
日本人は「〈米食悲願〉民族」だった
「米食は昔から日本の文化だから、守らなければならない」――。こうしたイメージについて、藤原さんは「戦前の昔からみんなが米を食べていたっていうのはフィクションです」と語ります。あらゆる階層の日本人が日常的に白米を食べられるようになったのは、高度経済成長期以降のことだといいます。
最新の学説では稲作は縄文時代に中国大陸から伝わったとされますが、藤原さんは「長い間、米を主食にできた人は限られていました」と語ります。農村部では、米は祭りや特別な日にしか食べられず、普段はヒエやアワといった雑穀や芋、あるいはカブを炭水化物として食べてきました。「ちょっと意外だと思いますけれども、1950年代までの日本では小麦も多く生産されていて、昔からうどんなどが食べられてきました」と藤原さんは話します。
明治に入ると、現在のミャンマーやタイやヴェトナムといった地域から、長細いインディカ米が輸入されることになりました。その結果、社会階層によって白米(ジャポニカ米)を食べる人と、あまり人気のないインディカ米を食べる人に分かれていったとのことです。
藤原さんは「インディカ米は白米と違ってねっとりしてないので不人気だった。そのため下層の人たちが食べるようになり、夏目漱石も『壁に使う土と同じ味でまずい』といったことを言ったりしていた」と説明します。「田舎に行けば行くほど芋や雑穀が食卓に上っていたし、東京では四谷や芝にあったスラムでは『残飯屋』という、陸軍士官学校とか海軍士官学校の給食の残りを安く売る店もありました」
米は食べたいが、生産量が限られるため輸入米に頼っていた戦前の日本。こうした状況を指して藤原さんは「日本人は『米食民族』ではなくて、『米食悲願民族』だった」と説明します。「米食悲願民族」は、東京大学の農業経済学者だった東畑精一の言葉です。
敗戦後、日本では米の増産が進み、高度経済成長期には多くの食卓に白米が並ぶようになりました。一方、余剰小麦の輸出政策をとったアメリカやカナダから小麦の輸入が進んだことも影響し、むしろ「米余り」の状況に陥り、減反政策が採られるようになります。
こうした経緯について藤原さんは「皮肉なことに、みんなが米を食べられるようになるくらい技術が進歩したときには、今度は外国産小麦を食べる文化が普及し、米を作らないよう生産調整に舵を切らざるをえなかった。『米食悲願民族』が『米食民族』になった瞬間、『小麦食民族』への道が開いていった。このアイロニーが歴史的に重要です」と指摘します。