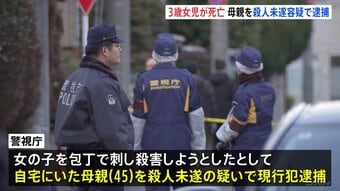「事故後も週に4回程度、運転している」
2等兵曹は弁護側の被告人質問で「事故などを起こすと、憲兵隊を呼ぶよう指示されていて、事故直後に憲兵隊を呼んだ」と証言した。また、我々の取材などから、2等兵曹が110番や119番通報をしていなかったことも明らかになっている。
日米地位協定では公務外の兵士が、事件・事故を起こし、警察が先に捜査を開始していた場合、日本側に捜査権があるとされている。この事故でも、警察官が憲兵隊よりも先に現場に到着し、捜査を開始していたが、2等兵曹は後から到着した憲兵隊に連れられ基地に帰っている。
一般的に日本で死亡事故を起こせば、免許取り消しになる。しかし、2等兵曹は「基地内だけ」と前置きしたうえで「週に4回程度、交際相手の車を運転している」と証言した。
米国で有効な運転免許証を持っている兵士らは、軍が発行する「許可証」を取得すれば、日本の公道で運転することができる。
警察庁によると、この「許可証」を持っている兵士らは日本の行政処分(免許取り消しなど)の対象ではないという。
警察が違反行為を取り締まっても、米軍側に内容を通知して、処分は米軍に委ねることになっている。今回の場合、米軍が2等兵曹の「許可証」を取り上げていなかったこともわかった。
横須賀基地の兵士に話を聞いたところ、「『許可証』を取得するには日本の交通法規などのテストに合格する必要がある」と話した。しかし、2等兵曹について、判決では「道路標識の意味を正しく理解していない」と厳しく指摘されている。
在日米軍が提出した“異例の書簡”に「司法の独立脅かす」と批判も
弁護側が提出した証拠にも、「異例の書簡」が含まれていた。
在日米海軍の法務部長から裁判官に宛てた書簡には、このように書かれていた。
米国の方針としては、仮に執行猶予付き有罪判決が言い渡され、それが受入国の法律に基づき確定した場合には、被告人を受入国から米国本土へ移送することを迅速に検討することになっています。再度逮捕されるような事案があった場合、長期の自由刑となる可能性があることから、最も例外的な事案を除いて、この措置が適切であると考えています。
遺族の代理人を務め、在日米軍の問題に詳しい呉東正彦弁護士は、判決後の会見で憤った。「米軍が組織として裁判官に対して、執行猶予付きの判決を求めたのだと受け止めた。一国の軍隊や政府機関が裁判所に書簡を出せば、司法の独立を脅かすような圧力がかかるのは間違いない」。
裁判官は執行猶予を付けた理由を「被告が事実関係と過失を素直に認め、真摯に謝罪していること。交通違反歴を含む前科前歴がないこと」などとした。書簡に記載されていた米軍側の「執行猶予付き判決が確定すると、迅速に帰国させる」という方針への言及はなく、書簡が判決に影響したのか否かはわからなかった。