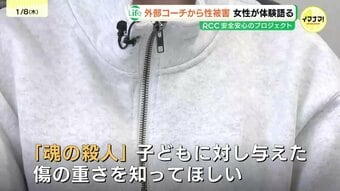雨が多くなるこの時期に警戒する災害の1つが「川の氾濫」です。広島県は6日、川が氾濫したときに浸水する高さの目安となる「洪水標識」を熊野東防災交流センター(広島県熊野町)に設置しました。住民の水害に対する危機意識向上が設置の狙いで、県は今後、洪水標識の設置を拡大させていく方針です。
標識には、近くを流れる川が氾濫した場合に浸水すると見込まれる最大値が示されています。
標識は感覚的に理解しやすくするため最大値と同じ高さに設置します。
県は、2023年から公共施設に洪水標識を設置する取り組み「まるごとまちかどハザードマップ」を始め、2025年3月末までに7つの市町に合わせて53箇所に設置しました。熊野町での設置は今回が初めてです。
洪水標識と同様に、防災で重要な情報を市街地に掲示するものに「海抜標識」があります。

佐藤勇希 記者
「所変わって海田町に来ています。瀬野川の河口付近、海からほど近いこの場所には、その土地の高さを示す海抜標識が設置されています」
海抜標識は、津波からの避難ルートを決める上で重要な情報で、各自治体が独自で設置しています。
海田町内では、海抜標識は100か所設置されていますが、洪水標識は10か所。
県全体でみても、洪水標識の認知度は、まだ低いといいます。県は、洪水標識を増やしていくことで、住民の水害に対する防災意識の向上につなげたい考えです。
広島県 土木建築局 河川課 児玉 光樹 主査
「水害の危険性をご認識いただいて、洪水が発生時、住民の避難の実効性を高めていきたいと考えています」
県は今後、洪水標識を設置する自治体を拡大させていく方針です。