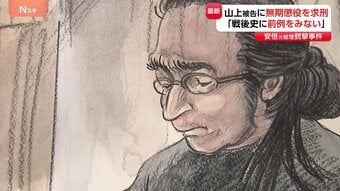安心感を求める若者とリスク社会
ここで、94年調査時点の若者が30年経って中年となり価値観は変わったのかどうか紹介したい。
ビジネス社会を生き抜くために必要なものとして、94年調査の若者も24年調査の若者も1位は「運やチャンス」2位は「実行力」と答えているが、3位は異なっている。94年調査では「要領のよさ」であり、24年調査では「協調性」である。
「協調性」について94年調査時点の若者では8位と重要視されていなかった。しかし30年経って中年となった彼らは、1位に「実行力」2位に「柔軟性」3位に「協調性」をあげる者が多く、現代日本が協調性を重視する社会であることがわかる。
協調性を重視することは一見問題がないようにみえるが、そうではない。先に述べたとおりの同質性を重視した協調性である。つまり、多様性の忌避、排他的な意味での協調性なのである。さらにいえば、ソーシャルメディアの普及、検索システムの高度化によって、個人は自身と異なる意見や価値観をもつ人々と隔絶されている。このような社会デザインによって、同質性への志向は強まっているだろう。
これは何も日本だけがこのような状況を示しているわけではないだろう。2020年代は、パンデミック、戦争、天災など激動の時代の再来である。このようなリスクの時代において個人はインターネット空間に閉じこもり、耳あたりの良いメッセージのみを享受し、異なる価値観や宗教・文化の社会集団を攻撃する社会現象が頻発している。
また多様性を謳う思想にも逆風が吹いている。あらゆる社会問題について、いまは争うことなく知性を結集して立ち向かわなければならない局面で社会は分断されている。この要因は同質性/同質的な社会へのあらがいがたい魅力であるのだろう。
リスクが高まり社会情勢が悪くなるなかで日本の若者は安心や安全を第一に求めている。日本の若者にとって、冒険やチャレンジをして人生におけるより大きな成功を手にする見込みが薄く、現在の生活が非常に悪いというわけではないため、彼らはそこそこの人生を望んでいる。
多くの若者が周囲と同じ程度の働き方、遊び方、考え方をもち、リスクを回避し、チャレンジしない社会を形成している。30年前と比較すると現代日本の若者はルールを遵守するようになり、逸脱した非行少年・少女の姿は消えた。闇バイトなどをする若者が話題となり、刑法犯少年の検挙率が増えた2024年度でも、1994年度の検挙率の4分の1である。
このように若者がルールを遵守し、まじめになったことは、戦後日本社会の成功面ともいえる。逸脱することなく、安心と安全を求め、そして家族と仲良く生きていくことは、ほほえましい傾向である。
価値観、文化・習慣などの同質性を希求する日本社会は、もしかしたら今が幸福の頂点であるのかもしれない。しかし社会の外側からのリスクに対して同質性の高い社会がより良く対応できるとは思えない。「個人的なことは政治的なことである」と掲げたのはフェミニズムの運動であったが、日本社会のサバイバル戦略にも同じことがいえるかもしれない。リスク社会をサバイバルしたいのであれば、社会はもっと家族関係と子どもの社会化に関心をもつべきである。
【参考文献】
博報堂生活総合研究所 2024『調査レポート2024 若者30年変化—Z世代を動かす「母」と「同性」』
品田知美 2016「子どもへの母親のかかわり」稲葉昭英・保田時男・田渕六郎・田中重人編『日本の家族1999-2009—全国家族調査【NFRJ】による計量社会学』東京大学出版会
<執筆者略歴>
羽渕 一代(はぶち・いちよ)
岡山県出身。2001年奈良女子大学大学院人間文化研究科単位取得退学。2018年博士(学術)。
専門はディア文化論、若者文化論。日本の若者のメディアの利用行動、恋愛や性行動、親密性に関する研究を行う。
主な著書に『現代若者の幸福―不安感社会を生きる』(共編著、恒星社厚生閣、2016年)
『「最近の大学生」の社会学』(共著、ナカニシヤ出版、2024年)
【調査情報デジタル】
1958年創刊のTBSの情報誌「調査情報」を引き継いだデジタル版のWebマガジン(TBSメディア総研発行)。テレビ、メディア等に関する多彩な論考と情報を掲載。原則、毎週土曜日午前中に2本程度の記事を公開・配信している。