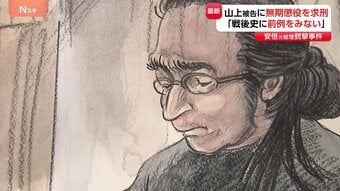同質性を求める若者
社会学の知見を援用して考えてみよう。家族の機能については、産業社会以降であれば子どもの社会化と家族のメンバーの心理的安定にあるとされている。家族内で父親は道具的役割、母親は表出的役割を担うことがその特徴として定説化されている。言い換えるならば、父親は経済的に家族を支え、母親は感情マネージメントで家族メンバーの心理的安定を支えるということになるだろう。
現代ではこの役割構造は崩れ、母親は道具的役割も表出的役割も担っているが、父親が表出的役割も担っているとはいいがたい。母親が道具的役割も担うようになったため、父親の存在感は家庭内で後退したといえる。
父親は経済的役割を担うと同時に家族内に社会的規範や異質な価値観をもちこむ役割を担っていると考えられてきた。父親の存在感が後退したことにより、子育てにおける社会的規範の伝達や異質性に対する寛容性を育てる契機が失われている可能性が考えられる。このような家族環境で育つならば、異なる価値観をもつ人と進んで交流していこうという若者が少なくなっても当然である。
異質な価値観や異なる文化や習慣をもつ人々と社会関係を形成することは、グローバル社会を生き抜くうえでは必須であり、また民主主義社会の形成においても重要な要件である。芸術や文化などのクリエイティブな発想やイノベーションの源泉であるともいわれている。
しかし自身と異なる価値観や文化を持つ人々とコミュニケーションをもち、社会を形成することは忍耐を必要とし、個人にとってあまり楽にできるものではない。同じ価値観や趣味、同じ言語を話す人と交流するほうがよっぽど楽である。民主主義を維持したり、クリエイティブでイノベーティブな活動をおこなったりすることによって個人に努力が必要とされたり、苦痛がもたらされるのはこのためである。
先にあげた調査の結果からみても、このような努力や苦痛を引き受けられない若者が増えている。30年前の若者は「人とは違ったようにしていたい」という価値観をもち、「人と同じようにしていれば安心だ」という価値観を大きく上まわっていたが、現在の若者は人と同じようにしていれば安心だと感じる若者のほうが多い。
これと同様に30年前は、働き方について「ベンチャービジネス」を志向する若者が多かったが、現在では「大企業」を志向する若者のほうが多い。
これらの生き方・価値観は人間関係のあり方にも反映されている。30年前は、居心地のいい組み合わせが「異性と二人でいること」と回答する若者がもっとも多かったが、現在では「同性同士の二人でいること」と回答する若者が激増している。くわえて「自分の考えと合わない人と一緒にいることは避けている」若者は30年間で57.2%から71.0%まで増えている。
現代日本の若者は、同じ価値観の人間関係のなかに閉じこもりたいのだろう。そして同じ価値観をもつ可能性が高い者は誰かといえば、家族(とくに母親)であることは容易に想像できる。
主となる価値観や生活習慣は、家族のなかで育まれるケースがマジョリティだからである。これにかかわり30年前と比較して、母親と共通の趣味をもつ若者も増えており、友だちよりも家族が大事だと感じる若者も増えている。