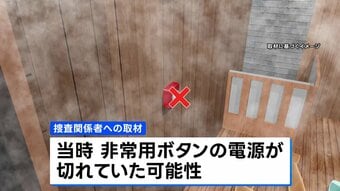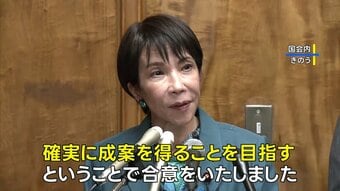父親より母親を尊敬する傾向が強いZ世代。仲良し母子、友だち母子の増加は、同じ価値観の中に閉じこもり、異なる文化、価値観との交流を望まない若者を生む。彼らは「人と違う」ことより「人と同じ」ことを志向する。そのような同質性の高い社会は、外部からのリスクに対応できるだろうか。弘前大学人文社会科学部の羽渕 一代教授による考察。
30年間で変化した親子関係
博報堂生活総合研究所(2024)は1994年と2024年に首都圏の19歳から22歳までの若者を対象にアンケート調査を実施している。この調査は、近年よく見かけるネット調査とは異なり、無作為抽出法を採用し、訪問留置自記式の学術的に意味のある調査である。
また24年調査は49歳から52歳の中年に対してもデータを採取している。これにより、90年代の若者と20年代の若者の比較、若者と中年との比較が可能となる。
調査結果のなかでもっとも衝撃的な変化は母親の存在感の高まりであった。同研究所は「Z世代を動かす『母』」もしくは「メンターママ」の存在を報告している。
94年調査では、母親よりも父親を尊敬している若者のほうが多かったが、24年調査では、父親よりも母親を尊敬している若者の方が多い。母親を尊敬する若者が45.4%から61.5%まで上昇し、いっぽう父親を尊敬する若者は53.5%から37.0%まで下落している。
「親の意見」を判断基準にするかどうかについても、アドバイス・忠告に従う相手として母親をあげる若者が父親をあげる若者よりも多くなった。けんかする相手も悩み相談もリラックスするおしゃべりも母親が非常に重要な存在になったと報告している。
ジェンダー的な観点からみても、94年の段階では息子は父親と行動し、娘は母親と行動する傾向があったが、24年になると、娘も息子も母親と行動することがわかった。このような現代の母親中心の親子関係について、他にも整合する調査研究がある。
24年調査の対象となった若者たちは、2002年から2006年に生まれている。彼らの母親世代を分析した品田知美(2016)は、どのような家族であっても、この世代の母親は子育てを他人任せにせず自身でおこなっていることを指摘している。
さらに母親が子どもと遊ぶ家族は父親も子どもと遊ぶという傾向があった。反対をいえば、母親が子どもと遊ばなければ父親も子どもと遊ばないのである。
そして子どもと関わる母親は高学歴の無業者(専業主婦)であった。少子化できょうだい数が少なくなったことも、これらの母親が育児にさらに手間をかけることに拍車をかけていた。
2020年代の首都圏の若者は、経済的に余裕があり、高学歴の女性を専業主婦として養える家庭で、丁寧に手をかけられて育てられているのだ。
24年調査の若者の親は10歳代から20歳代でバブルを経験しており、バブルが崩壊しても経済的に余力のある時代にパートナー形成・家族形成をしている。進学率、親との同居率が高まり、仲良し親子(=友だち親子)が出現した時期でもあった。
仲良し親子を経験した若者がやがて親となったとき、父親の存在感は薄れて、絶大な母親の影響力が親子関係の特徴となった。このような仲良し親子(=母子)を中心とする日本社会はどのようなかたちをしているのだろうか。