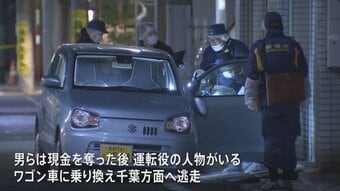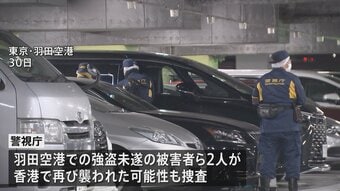「9年前にし損ねた宿題をですね、今こそやるべき」
玉木代表:
で、今日ちょっと資料を配ってますが、9年前日本農業新聞で、小泉当時、自民党農林部会長と、紙上対談をさせていただいた。9年前のお互いちょっと若いんですけどね。結構若いんですが、そこで実は米政策についてですね、話をしてまして。そこで、下線引いてますけども、まず、大臣が2018年ですね、米政策の歴史の大きな転換点となる。これいわゆる減反廃止をしたとされる年です。国が生産数量目標の配分をやめ、需要に応じた生産をしてもらえる環境づくりをしていく、何としてもやり遂げるとおっしゃってるんですね。それに対し私が下に書いてますが、価格は市場で決めるべきで人的に関与する政策は長続きしないと。特にその土地利用型作物ですね米麦大豆は、どうしても販売価格が生産費を下回るのでそこは所得補償して営農継続できるようにすべきだと。ちょっと下線引いてませんが左のですね、1番上のところ、自由貿易と整合的な農政にしていかなければいけない。価格のコントロールから卒業すべきで何らかの所得補償が必要になる。米に対する直接支払いの在り方で、ある程度一致できれば農家も安心するということを9年前に言ってます。
私は当時ですね、非常に大きな期待を集めて、農政改革に取り組んだ、小泉現大臣ともいろいろやりとりさせていただきましたが、この減反廃止なんですけど、いわゆる供給を調整して価格をある意味人的に一定程度高めてですね、ある種消費者負担で、農家の所得を確保していくっていう政策をそこでやめて、生産調整をやめるとおっしゃってるんですが、でもその後行われたのは御存じのとおりですね。生産数量目標を農水省とJAで、全国回ってですね、配分割を事実上していき、また、特に餌米ですね。飼料用米に対して単当たり10万5000円つけて、あるいはいろんな転作奨励しながら、主食用米の供給を絞っていくって政策は継続したんですよ。
このことが私は、なかなかお認めになりませんが、やっぱり米の不足、そしてインフレになったことによる米の高止まりということの遠因になってんじゃないのかというふうに思うので、9年前にし損ねた宿題をですね、今こそ、大臣やるべきじゃないのかな。ただ、単に需給調整から国が手を引いて価格コントロールすると下がりますそれは、これはもうマクロ経済学でいうとものが増えたものは、価格が下がるので。そうすると再生産可能な、所得が保障出来ないので、今度は政策で直接農家の所得を保障していく。
国が価格をコントロールするという価格政策から、価格のコントロールから手を引いて、それからつくりたい人はつくる、あるいはまさに需要に基づいて作付けしていく、その代わり、値段の低下に対しては、直接政策で所得補償していくという所得政策に、ある意味大きく今度こそですね、政策転換をしていかないと、低くするのも高くするのも、大変じゃないですか。あるときは高く保たないと農家の再生産可能な所得保障出来ないし、でもあるときは今回みたいに上がったら下げることに一生懸命で、そのプライスっていうものに対して、国家が上げるにせよ下げるにせよ関与して、てんやわんやになってること自体ですね、資本主義じゃないですよ。だから、今回9年前こういうやりとりをしてますが、あの時、実はやっていればですね、今回の米不足も米の高値も防げたんじゃないかな。という思いがありますが、9年たって振り返って、いかがでしょうか。
小泉農水大臣:
9年振り返って、若いですね。このときもお世話になりました。今あのときやらなかったっていうことは、一つ言えるのは、やはり部会長という立場、この中でできることと、そして大臣としてできること、これはおのずと、やはり権限が違いますので、今回より重い、結果責任が伴うとこれは間違いありません。
そして、当時思っていたことだけども、出来なかったという思いを抱えながら、今、農政に向き合ってるのは、私だけではなくて実は石破総理が非常に強い思いを持っています。当時から、方向性として、今玉木代表がお話をされたような思いを持ち続けて、農林水産大臣も当時やられたのが石破総理で、そして今回、石破総理がこれからの農政を変えていきたいという中で、私は任命を受けました。
今後、総理ともよくお話をしながら、令和9年に向けて米政策も変えていこうと。こういった中で、先ほど申し上げたとおり、様々な課題をテーブルにのせて、与野党の皆さんとも垣根を越えて議論をしなければいけないと申し上げたとおり、やっていくべきことがあると思いますので、まず目の前この米の価格を落ちつかせて、そして今御指摘の、中長期でこれからどのような米政策に転換をしていくべきなのか、ここは、これからも、重要な課題として取り組ませていただければと思います。