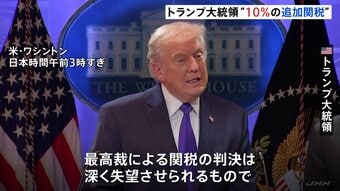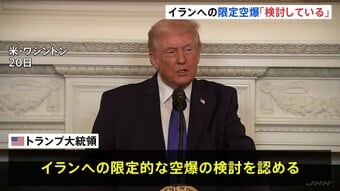数々の話題作で劇伴を手がけてきた作曲家・木村秀彬氏。情感をすくい上げる繊細なスコアと、物語の温度に寄り添う構成力を強みとし、テレビドラマから映画、アニメまで幅広く活動を続けている。
現在放送中の日曜劇場『キャスター』(TBS系)の劇伴も手掛けている木村氏。自身も「一番得意じゃなかった」と語るテーマ曲に、今なぜ重心を置くのか。劇伴の“雑味”を大切にする理由とは。そして、音楽が人の記憶に残るとはどういうことか。静かな音の裏側にある、木村氏の確かな信念と創作の軌跡に迫る。
劇伴が若い世代に与える影響

「ドラマって基本、ワンクールで終わるじゃないですか。3か月で放送が終わると、音楽も自然と切り替わっていくし、どんどん新しい番組も出てくる。そういう中で作品とリンクしている曲で“あのドラマといえばこの曲”って残っていくと思うんです」
単なるBGMとしてではなく、作品と結びついて“心に残る音楽” を目指している木村氏。そうした中で近年、うれしい反応があったという。それは、演奏楽器を通して音楽に親しむ若い世代からの声だ。
「今回はサックスを使っているんですけど、中学・高校生くらいの吹奏楽部の子たちが“サックスだ!”って反応してくれたり。あと、ティンパニーを担当している方が“この曲、ティンパニーがめちゃくちゃ鳴っているから聴いてみよう”とか“ドラマを見てみよう”とか。そういう反響をもらうと、すごくうれしいですね」
中でも、思春期の音楽体験が与える影響は大きいと感じている。
「中高生くらいで出会った音楽って、一生残るらしいんですよ。その時期の記憶って、その人の“音楽の核”になるというか。だから、そういう年代の人たちが、自分の音楽を“思い出の1曲”として覚えてくれたら、それが一番うれしいなって思っています」