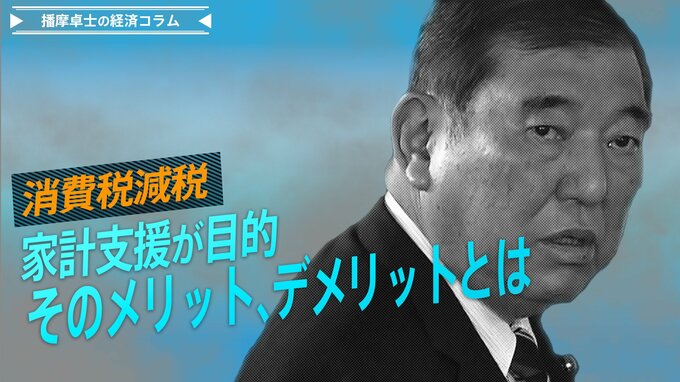物価高への対策として、野党だけでなく与党内からも高まっている消費税減税論に対し、石破総理大臣が実施しない意向を固めたと報じられました。税金をめぐる議論には常にメリットとデメリットがあり、最後は、国民の「判断」の問題です。私なりに問題を整理してみました。
「物価高対策」ではなく「家計支援」
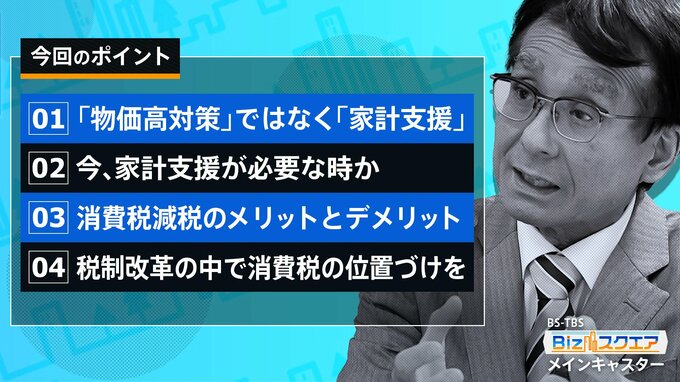
減税の議論では、まず、「目的」をはっきりさせることが重要です。「物価高対策」という表現が一般的に使われていますが、私は、消費税減税を「物価高対策」と呼ぶのは正確ではないと考えています。
「物価高対策」とは、「物価を抑える」政策です。ガソリンや電気・ガス代に補助金を出したり、公定価格を引き下げたりすることが「物価高対策」になります。確かに食料品の消費税を一時的にゼロにすれば、名目価格は8%分下がりますが、それは1回限りのことで、1年経てば、インフレ率への効果はなくなります。
むしろ、減税であれ、給付金であれ、大型財政出動によって、需要を刺激すれば、むしろ物価押し上げ効果も持つことにもなります。従って、消費税減税を「物価高対策」と呼ぶのは適切ではありません。
消費税減税は、賃金が物価に追いつかない、つまり実質所得のマイナスが続く中で、家計の負担を減らすことが目的です。家計支援によって、消費の失速や景気後退を避け、需要を下支え、創出することが目的なのです。その意味では、「家計支援」、「需要創出」が、今必要かどうかが、まず議論されるべきでしょう。