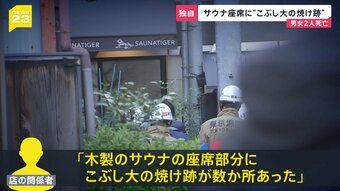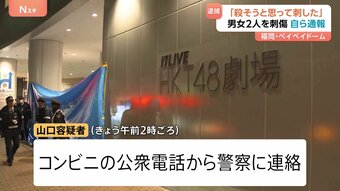基調的物価が「持ち直す」根拠なし
今回の経済見通しは、期間後半に、通商政策の不透明さが解消されて成長が回復し、それにつれて、基調的物価も再び上昇していくというストーリーになっています。植田総裁も「トランプ政権の関税政策そのものの不透明性が高く、見通し自体が変わる可能性もある」と強調していました。
確かに、理屈としては、トランプ関税の霧が完全に晴れ、何もなかったかのように、「景気もインフレも、心配ない」といった世界が再びやってくる可能性が、ゼロとは言えません。しかし、普通に考えれば、トランプ関税による成長や物価の下押しの影響はそれなりに続き、簡単に昔に戻ることはできない“リスク”の方が高いはずです。
そもそも、今回の日銀の見通しも、「通商交渉が一定進展しつつ、ある程度の関税政策が残る」という前提で作成されたというのですから、むしろ下振れリスクを警戒すべき見通しです。その意味では、年内どころか、来年に利上げができる、具体的なイメージなどないに等しいと言えるでしょう。
消えた「賃金と物価の好循環」
今回の日銀の見通しでは、基本的見解の文章の中から、「賃金と物価の好循環」という言葉がなくなりました。成長や企業収益が下押しされることが明白な時に、そうした言葉は適さないと判断したのでしょうか。
植田総裁は、これまでの「誤算」として、去年の半ばから再び食料品の価格上昇が目立ってきたこと、賃金上昇のサービス価格への波及が思ったほど伸びなかったことの、2つを具体的に挙げ、「好循環」実現の遅れを認めざるを得ませんでした。
しかし、食料品価格の再高騰は、去年再び円安が加速したことの影響が大きく、そうしたコストプッシュによるインフレ加速が実質賃金マイナスを招きました。そして実質賃金の伸び悩みが、サービス価格の価格転嫁を遅らせていると言えるのではないでしょうか。
だとすれば、それは、金融正常化の遅れなど日銀の政策運営にも責任の一端があると言うことです。利上げ開始が遅れ、そのペースも遅いことが、円安を通じて、「好循環」の芽を摘んだ面はなかったのでしょうか。