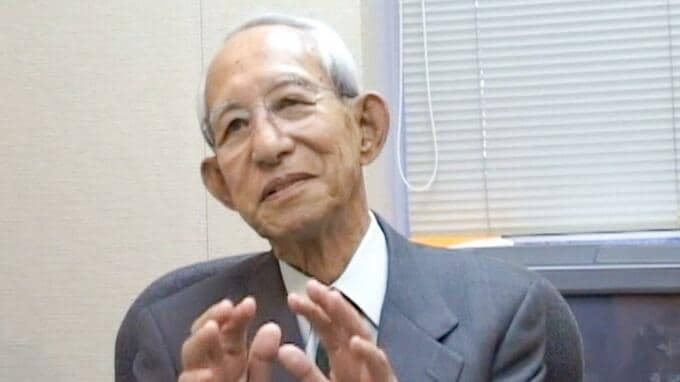政府の圧力が…
大山 出来たフィルムはどんどん送って……。
田 いや、それが出来ないんです。ですから、フィルムは背負って帰って来て、それが大変でした。その整理をするのに、端からニュースコープで放送していって、本当に使える画像を選り出して作ったのが「ハノイ 田英夫の証言」という特別番組です。
大山 それで、いろいろなことが起きますが、具体的にどういう……。
田 放送したのが昭和42年(1967年)の10月30日ですが、それから1週間か10日ぐらいのちに、たまたま自民党のいわゆる郵政族という、今でもあるようですが、その大将が当時は田中角栄さん(1918〜1993)。それで、事務局長のような役割が橋本登美三郎さん(1901〜1990)。そういう方はテレビ局の幹部と時々懇親会のようなことをやっておられた。たまたま、私の放送のあった直後にそれがあって、今道社長以下が出られた。そしたら、報道局長が翌日教えてくれたんですが。
大山 島津さんが。
田 ええ。「きのうは橋本さんが『なぜTBSは田君をハノイにやってあんな放送をさせたんだ』と文句を言うから、今道社長はいきなり『いや、TBSは報道機関なんだからニュースのある所ならどこへでも行く。あれは私が命じてやらせたんだ』って開き直られて、座が白けてたよ」なんてことを私に教えて下さって。これはまあ、来たかなと思ったんです。
しかし、日本では本当に初めて北ベトナム側からの状況を生々しく伝えて、その中身については、全くカメラには嘘は撮らないんで。「アメリカは負けてますよ」と言ったわけではなく「こんな状況ですよ」と言ったのはまさに真実の報道だという自信はありましたから。
ただその後、半年ぐらいのあいだに、いろんな攻撃が権力側からありました。例えば、JNNネットワークの地方局の番組審議会の意見として「今度のエンタープライズ入港についてのTBSの報道は偏向してる」というふうな意見書が届いたりね。ちょうど翌年の43年の1月に佐世保にエンタープライズが入港して、原子力空母ですから騒ぎが大きかったし※、全学連※※の共産党じゃない方※※※が非常に激しく抵抗した。
※ アメリカ海軍の原子力空母エンタープライズが長崎県佐世保港に入港。これに反対する政党、学生、市民による激しい抗議活動が起きた
※※ 全日本学生自治会総連合
※※※ 全学連主流派、日本共産党を批判して新しい左翼運動を目指していた共産主義者同盟などが主導権を持っていた
私はその時も現場へ行って。いろいろ圧力があることは自覚してましたから、古谷綱正さん※(1912〜1989) にスタジオにいて頂いて。
※ 「ニュースコープ」キャスター 毎日新聞出身
田 それで、まず私がいきなりホットな現場の空気を伝えてしゃべる。そのうえで、いろいろな目で見られてもいけないので、一回クールなスタジオを通して、古谷さんと私がしゃべる形でやってみたんですけど、それでも、そんな意見が来る状況は続いてました。最後、その年の3月にこれは別の、成田の反対運動をやってる農民の皆さんのプラカードを……。
大山 (TBS取材班が)乗っけたという。
田 それが直接の引き金になったんです。私には関係ないことだったんですが。結局最後のとどめは、プラカードを運んだ時に、あとで分かったんですが、警察の報告は「TBSは凶器を持った農民を運んでいた」となっていた。このくらいのプラカード※ が凶器ということになって。
※ 「週刊誌の倍ほどの大きさのベニヤ板に1メートル前後の棒を打ち付けたもの」(「お前はただの現在に過ぎない」萩元晴彦 村木良彦 今野勉 著 )
それを受けて、当時の自民党幹事長だった福田赳夫さん(1905〜1995)が、夜の、これはオフレコ会見なんですけども、まぁオフレコだから言ったんでしょうけど、TBSがこういうことをした。「こういう局には再免許を与えないことも考えなくちゃいけない」という発言をされた。
そこにTBSの政治部の人もいましたから、すぐ報告がいって、翌朝すぐに今道社長に私が単独で呼ばれたんです。何だろうと思って行ったら「実は昨日、こういうことがあって、今まで私も言論の自由を守ろうと報道の皆さんと一緒に頑張ってきたけども、これ以上やるとTBSが危なくなる。残念だけど今日で辞めてくれ」と、そういう言い方でしたね。
で、すぐに島津報道局長と相談して、今日で私が辞めるなら最後に挨拶で言わなくちゃいけないとなったら、重役室の方から「それもならん」と。考えたあげく、いつもは「それでは、また明日」と言っていたのを「それではみなさん、さようなら」とこう言ったんですけど、突然画面から姿を消したという結果になりましたね※。
※ 田英夫の突然の降板は、上記のいわゆる「成田事件」に関わった担当者への厳しい処分や「ハノイ 田英夫の証言」などを制作した報道部ディレクターらの人事異動などでくすぶっていた報道局組合員の不満に火をつける結果となり、以後100日近い労働闘争に発展していった。