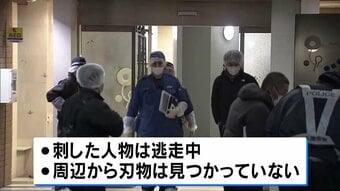放送界に携わった先人たちのインタビューが「放送人の会」によって残されている。その中から、日本初のニュースキャスターを務め、北ベトナム側から見たベトナム戦争の実態を現地ハノイから伝えて大きな反響を呼んだ、田英夫氏のインタビューをお届けする。聞き手はドラマプロデューサー、演出家の大山勝美氏(故人)。
日本初のニュースキャスターに
大山 (学徒出陣で)特攻隊に行って、それから共同通信の文化部長に。そこらへんから、お話しいただければ。
田 文化部長の直前は社会部長だったんですが、これが大変忙しくて24時間勤務みたいな状態でした。それが文化部長になったら本当に暇になって、丁度そんな時にTBSの報道の方から「新しい報道番組を作るから、ちょっと相談に乗ってくれませんか」というお話がありました。
で、のこのこ出て行きましたらね、コーヒー飲んで、実はもう(スタートが)1カ月近くに迫ってたんですが「ニュースコープ」※っていう名前もまだついてなかったのかな、とにかく、新しい企画でやると。「ついては、ちょっとスタジオに来て下さい」と、そのままスタジオに連れて行かれて。
※ 「JNNニュースコープ」夕方6時半から全国ネット放送。キャスターが伝え手となる日本で初めてのニュースショーと言われる。キャスターが交代しながら1962年から1990年まで27年半放送された
それが実はオーディションだったんですね。20人近くオーディションして、私が最後の方だったらしいんです。それで「実はこういう番組でニュースキャスターという新しいしゃべり手でやろうと思うんです。是非やって下さい」と、こういう話で。
共同通信にいながらやるわけですけれど、文化部長というのは正直なところ、夕方からいなくなっても、あまり支障はなさそうでしたから。いわばアルバイトのような格好で。「週3回は夕方5時に僕はいなくなるぞ」と部員の皆さんに言って了解してもらって、やり出したんです。
ところが、やり始めたら実にこれは大変なことでね。そんなアルバイトぐらいの姿勢でやれるもんじゃない。私自身もテレビでしゃべったことはほんの数回しかない、素人もいいところなんです。ニュースを書く方は、先輩に鍛えられながらある程度やっていましたが、しゃべるっていうのはこんなに難しいもんかと。
アナウンサーで育った方は原稿を読みながら、カメラの方を向いていることが出来る余裕も技術もあるんでしょうが、私なんかは読み出したら下を向いたっきりで、顔が上がらない、そういうことに気がついたり。しゃべる技術、それに本当に戸惑いました。
大山 原稿は独自ですか?それとも毎日新聞とかいろんな情報から選択っていうか。
田 当時、すでにTBSの報道はかなり取材能力がありましたね。
大山 昭和37年……。40歳ぐらいですね。
田 そうです。その頃は、まだ特定の新聞社と深い関係を作っている状況ではありませんでした。通信社のニュースは参考として流れてきているにしても、そのニュースの選択の段階から私も加わる。ただ、アルバイト感覚でやってた最初の一年ぐらいの間はそれが出来なくて、夕方5時頃行くともう原稿が揃っている。それは本当に無責任な話だったと思うんですよ。
初めは、原稿を見ながらしゃべっていたんですが、ニュースキャスターという肩書でやるわけですから、アナウンサーのようにサーッと読んでるんじゃ視聴者に親しみがないし、なんか流れて行っちゃう感じがあったんです。そこが一番大事なところだろうと思って最初にやり出したのは、原稿を読みながら、社会部デスクをまたやり出したみたいに直したりしつつ、自分で画用紙にマジックインキでやや大きい字で、例えば人の名前や住所とかをメモのように書いたんですよ。
カメラのレンズの下に譜面台のようなものを作ってもらって、そこにその画用紙を何枚も立てかけて、若い人がそれをめくってくれる、まさに紙芝居方式をやりだしたんです。そうすると目線が下がらないということが一つありました。
もう一つは、今度はマイナスの方で「あなたのを聞いてると、ウーとかアーとか入って聞き苦しいぞ」というご批判のお手紙をたくさん頂きました。それは、結局メモを見ながらしゃべってるからなんですね。
こっちは悔しいけれど、本当のことを言うのも癪だし、そこでこれは非常にうまい言い訳だったと思ってるんですけど「人はそれぞれ頭の回転や理解する速さが違うんだ」と。
だから立て板に水でしゃべったら、特にニュースは理解しにくいだろう。読む場合なら自分なりの速力で読めるけど、しゃべるのを聞いて理解するには、しゃべり手の方もただ読むんじゃなくて、自分の頭の中で考えながら読んでいくのが聞き手の理解のためにはいいと思ってやってるんだって。そうすると当然、頭の中で文章を作る間合いでアーとか入っちゃう、そういう言い訳を自分ではしてたんですね。