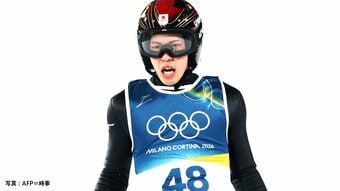魅力あるクルマを適切なタイミングで 根源はカルロス・ゴーン元会長に行き着く
日産の業績不振の要因の一つは、市場のニーズにかなうクルマを適切なタイミングで投入できなかったことも大きい。
例えば北米地域では価格の高さやインフラ不足などからEV=電気自動車が伸び悩んでいる一方、ハイブリッド車が急成長している。しかし日産はこの地域でハイブリッド車が出せず他社と比べて在庫を抱え、大幅な奨励金をつけてなんとか売りさばいているという有様だ。
魅力あるクルマを適切なタイミングで市場に投入するのは、まさにエスピノーサ次期社長がこれまで担当していた商品企画の領域だ。
これについてエスピノーサ次期社長は「開発を早くできなかったことは後悔している」と反省の弁を述べ、「大企業を変革するのは簡単ではない、決意を持って変えよう思っている」とこれからの改革に対して意気込んだ。
課題の多い日産自動車だが根源はカルロス・ゴーン元会長に行き着く。
「新車投入が長引き、売れるクルマがない」というのはゴーン時代の販売拡大施策を引きずっているのも一つの要因で、EVに重きを置き北米でハイブリッド車を軽視したのもゴーン時代の負の遺産とも言える。
そしてゴーン元会長の逮捕以降、「意思決定の透明性を図る」として社外取締役が主導権をもつ取締役会が構築されたが、今回のホンダとの経営統合をめぐり取締役会のなかで思惑が錯綜。日産のある幹部は「自動車のビジネスを知らない人たちが取締役会の半数以上を握っていてうまくいくわけがない」と嘆いた。