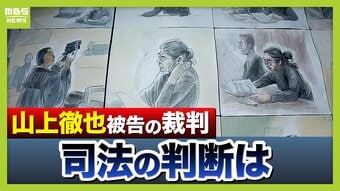20種類以上の粒子を試作し、ナノ粒子にたどり着く
2年生の間に取り組んだのは、独自の磁石を作ること。硝酸鉄に水分子が9個結合した九水和物、アミノ酸のグリシンなどを調合した上で、イオン交換水と混ぜて熱していくことで、砂鉄のような粒子を作っていった。

できた粒子については、メチレンブルーと呼ばれる溶液に入れて浄化能力を確認するほか、顕微鏡を使って状態を確認する。一連の作業には6時間ほどかかるものの、できるのは5グラム程度のわずかな量だ。しかも、調合を変えながら、何度も実験を繰り返していく。これまで作った粒子は20種類以上に及んだ。

2年生の時点で磁性を持った粒子ができたものの、汚水の浄化に使ってみると30日もかかった。その原因を調べると、粒子が大きいためだと分かり、より小さなナノ粒子を作る必要があった。
そこで、3年生になってからは学校側にマントルヒーターという機材を購入してもらい、ビーカーに入った溶液を液面下で燃焼させる溶液燃焼法を試すようになる。その結果、「酸化鉄磁性ナノ粒子」を作り出すことに成功した。


研究の画期的な点を、平澤准教授は次のように評価する。
「光触媒で汚水をきれいにする発想は、以前から存在します。でも、使った後の物質をどうするのかが課題でした。それを磁気光触媒にして磁石で回収できるというアイデアは、設備の導入やメンテナンス技術者も必要なくなり、持続可能な社会に貢献できる技術です」