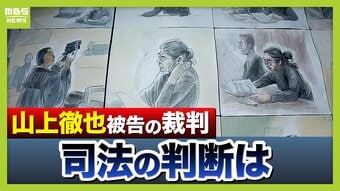将来は発展途上国の汚水を飲み水に
この研究成果は80年以上の歴史を持つ学会の「化学工学会」で発表した。高専の低学年の生徒による発表は極めて珍しい。また、2024年の高校生・高専生科学技術チャレンジ(JSEC)では協賛社賞を受賞。世界最大規模の科学コンテストである国際学生科学技術フェア(ISEF)の日本代表にも選ばれ、木村さんが2025年5月にアメリカで開催される大会で発表する。
現在は企業と共同研究を進めていて、工場から排出される汚染水の浄化に取り組んでいる。その延長線上には、下水処理への応用も考えられる。
さらに将来的に期待されるのが、汚水を飲める水に変えることだ。開発した「酸化鉄磁性ナノ粒子」には、もう一つの特長があると木村さんが説明する。
「川などを浄化した際に、粒子を100%回収するのは無理です。その粒子を魚が食べて、さらにその魚を人間が食べても大丈夫なの、とよく聞かれます。実はこの粒子は、人体に影響を及ぼさない生体適合性を持っていることが平澤先生の研究で分かっていて、生態系を壊す不安はありません。飲めるくらいまで浄化できれば、多くの人が助かるのではないかと思っています」
平澤准教授は、生体適合性に加えて、保存しながら浄化する点にも大きな利点があると指摘する。
「発展途上国では飲み水を遠くから運んできても、保存している間にすぐ駄目になってしまうと聞いています。そのときに、この粒子を入れておけば、保存している間に水質は悪くなるどころか、どんどん浄化されます。水に困っている多くの人たちにとって、便利なものになるのではないでしょうか」
木村さんと加藤さんは、春から高専の4年生になる。「将来は研究職に就きたい」と話す2人は、今後も「酸化鉄磁性ナノ粒子」の浄化能力の向上に取り組んでいく。
(「調査情報デジタル」編集部)
【調査情報デジタル】
1958年創刊のTBSの情報誌「調査情報」を引き継いだデジタル版のWebマガジン(TBSメディア総研発行)。テレビ、メディア等に関する多彩な論考と情報を掲載。原則、毎週土曜日午前中に2本程度の記事を公開・配信している。