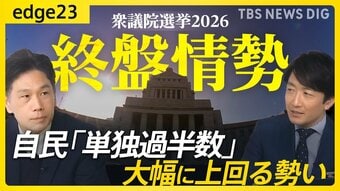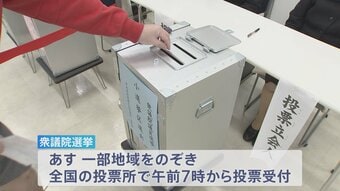■離島を守り抜く“対処力”

中国との国境付近に位置する南西諸島は、まさに「防衛の最前線」ともいえる。こうした離島が非常事態に陥った際、全国各地から陸上自衛隊や各自衛隊の装備品を輸送し、迅速に必要な部隊を展開する“対処力”が求められる。
まず離島に危機が迫っている場合、事態が発生する前に部隊を展開させるため、なるべく早期に輸送を完了させなければならない。事前展開の輸送には、海上自衛隊の輸送艇「LCU」などが用いられる。しかしこのLCU、現在日本にたった2隻しか配備されていない。防衛省は23年度予算の概算要求で、新たにLCU2隻を取得するための経費約161億円を計上した。
2024年度には海上自衛隊の呉地区に、LCUなどを運用する「海上輸送部隊」が新編される予定だ。「海上輸送部隊」は、海上自衛隊だけではなく、陸上自衛隊も参加し「共同の部隊」となる。実際に離島への上陸を遂行する陸上自衛隊が運営に携わることで、艦船乗組員の確保に資するとともに、輸送に一定の時間を要する海上輸送力を強化するのが狙いだ。すでに、LCUの調達要求に関する事務は陸上自衛隊が行っている。また「海上輸送部隊」に配属予定の陸上自衛隊員は、2019年度から海上自衛隊で、艦船の運航に必要な教育を受けている。
一方、既に非常事態が起こってしまった場合は、海上自衛隊第1輸送隊が運用するエアクッション艇「LCAC」などを用い「水陸両用作戦」を実行する。陸上自衛隊の水陸機動団や戦車を乗せて上陸し、LCACから直接飛び出した部隊が、敵に占領された離島の奪還をはかる。
LCACは、最大で人員約200人、車両2~3台をのせることができ、現在日本には6隻配備されている。足場の悪い状態でも上陸することができるため、津波に襲われた海岸から支援物資を運搬することもでき、東日本大震災で使用された。
2022年6月、日本で初めて開催された「太平洋水陸両用指揮官シンポジウム(PALS)22」でも、参加国にLCACが公開された。シンポジウムの開会式では吉田陸上幕僚長が、インド太平洋地域における「the major power competition(=大国間競争)」に言及した上で、水陸両用作戦の意義を強調。「大国間」がアメリカと中国を暗示しているのは言うまでもない。
■求められる“離島防衛”

現行の国家安全保障戦略では「台湾海峡を挟んだ両岸関係は、近年、経済分野を中心に結びつきを深めている。一方、両岸の軍事バランスは変化しており、両岸関係には安定化の動きと潜在的な不安定性が併存している」と記されている。もはや“不安定性”は顕在化し、“安定化”は鳴りを潜めているのではないだろうか。
年末まで残り3か月。安保関連3文書の改定に向け、岸田総理は「国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議」を設置した。9月30日の第1回会議では、ある有識者から「防衛力強化の主要な目的は、台湾有事に際して国を守れる力をつけるということだ」という意見があったという。
“離島防衛”のあり方そのもののみならず、防衛費の財源など問題は山積みに思えるが、真に国民を守れる力を培うことができるかが問われている。
(TBSテレビ政治部 防衛省担当 岩本瑞貴)