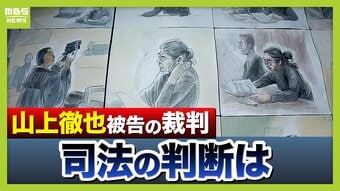「被災地出身の記者」だからこそ
私が被災地に記者として足を踏み入れたのは2024年1月2日、地震の翌日です。地元の風景はまるで知らない町のようでした。陥没した道路、大きく飛び出たマンホール。あったはずの建物は崩れ落ちてがれきとなり、町を通ると木材の香りがしました。がれきの隙間には家具や靴、食器などが挟まっていて、当たり前の生活がほんの少し前までそこにあったことが分かりました。


住民はみな避難所に身を寄せていて、町全体がシーンとしていました。時折、緊急車両のサイレンが響くだけでした。
避難所にいた、薄着でサンダルを履いたおばあちゃん。「もう帰る場所もないげん」と悲しそうに笑いながら話してくれました。記者として失格だと思いながらも、涙は止められませんでした。返す言葉は見つかりませんでした。
2日は、通っていた飯田高校がある珠洲市で車中泊をすることになり、停電が続く町から空を見上げると満天の星が美しく輝いていました。
記者として、地元を取材する。あまり馴染みの無い土地では記者の平でいられたと思います。
一方、友達や恩師、お世話になった方々が大変な状況で生活する中「取材させてくれ」と連絡するのはとても嫌でした。「歩生の頼みなら」と言ってくれる方もたくさんいて、私は自分との関係性やみんなの優しさを利用しているのではないかとよく自己嫌悪になりました。
それでも記者を辞めなかったのは、私が地元のためにできることで一番の影響力につながるのが記者であり、記者を続けることだと思ったからです。
ただの平歩生では、ボランティアに行ったり、募金したりすることで精一杯でした。「被災地出身の記者」という肩書でテレビやネットニュース、ラジオで放送することで、少しでも関心を持ってくれる人がいるなら。それが私が記者を続ける理由でした。
私は1年を通して、珠洲市に暮らす高校時代の同級生の男性を取材しました。被災地に暮らす子供たちの笑顔を守るために、運動会や歌手を呼んでの被災地ライブ、停電した町に灯る夢ちょうちんなど、男性は意欲的に活動していました。同級生同士だからこそ生まれる会話がたくさんあったと思います。ほかの人ではできない取材ができたと思っています。

一方で、同級生を取材する度、どこか後ろめたさを感じていました。私は大学進学を機に奥能登を離れ、金沢市で生活しています。結婚し、もう、能登に戻ることはありません。故郷であることには変わりありませんし、今も大好きなまちですが、「私は能登を捨てた」そんな思いを持ちながら今も能登に暮らす友人を「同じ」能登出身として取材することに後ろめたいような、恥ずかしいような気持ちを感じていました。