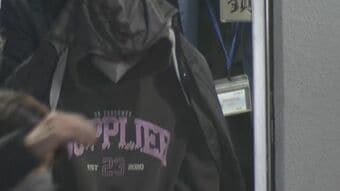放送コンテンツに求められるもの
さて、2025年の放送コンテンツはどのように展開するであろうか。容易に予想されるのは、インターネット空間との連動・展開が、より一層進むことである。それは先に見たCTV化とも重なる。
また、放送コンテンツの出し口については、2次利用、3次利用といったその展開の過程で、制作当初から国内のみならず、海外をも意識した計画が増えていくことになるのではないか。
若者の「テレビ離れ」や、「テレビはオワコン」といった声がある一方で、日本における映像コンテンツの制作能力では、いまだにテレビ局がその先頭を走っていることは確かである。そのことをあわせて考えると、テレビ放送らしい、テレビ放送ならではの映像コンテンツのプレゼンスをどう示せるかが、一つの試金石かも知れない。
そのことからすると、今年は、終戦から80年目でもある。また、昭和になってから100年目。「昭和100年」でもある。特定のイデオロギーに偏ることなく、丁寧な取材と事実に基づいての歴史の振り返り、そして戦後史を振り返る映像作品を作ることができるのは、現状においては、既存のテレビ局が、最もその力のある組織といえる。
その意味においては、テレビ放送の制作力、取材力、社会への問題提起力が試される年ともいえる。
同様に、インターネットとの融合時代であるからこそ、生番組の力が最も光るジャンルの一つがスポーツ中継である。昨年の日本のテレビ・スポーツは、ドジャース・大谷翔平選手の活躍に随分と依存したところもあったが、2025年もその状況は続くのか。大谷人気がどこまで続くのかはわからないものの、佐々木朗希選手が、ドジャース入りを決めたこともあり、話題には事欠かないだろう。
また、今年国内で開催される国際的なスポーツイベントとして注目されるものの1つは、何といっても、9月に東京で開催される世界陸上だろう。世界陸上は、2007年の大阪大会以来、18年ぶりの日本での開催となる。昨年のパリ五輪で活躍し、注目選手となったやり投げの金メダルリスト・北口榛花、中・長距離の田中希実、競歩の池田向希らへの期待は大きい。
放送コンテンツのパワーを示すことこそが、テレビの未来を切り拓くことになろう。その意味においても、信頼性もある、面白い放送コンテンツを次々に社会に発信して欲しい。
<執筆者略歴>
音 好宏(おと・よしひろ)
上智大学新聞学科・教授
1961生。民放連研究所所員、コロンビア大学客員研究員などを経て、
2007年より現職。衆議院総務調査室客員研究員、NPO法人放送批評懇談会理事長などを務める。専門は、メディア論、情報社会論。著書に、「放送メディアの現代的展開」、「総合的戦略論ハンドブック」などがある。
【調査情報デジタル】
1958年創刊のTBSの情報誌「調査情報」を引き継いだデジタル版のWebマガジン(TBSメディア総研発行)。テレビ、メディア等に関する多彩な論考と情報を掲載。原則、毎週土曜日午前中に2本程度の記事を公開・配信している。