1月13日の夜、日向灘で起きた地震の速報に、RKB毎日放送の神戸金史解説委員長は血の気が引いた思いをした。折しもこの日の日中、1995年に発生した阪神・淡路大震災の取材で出会った人たちと、連絡を取り合っていたという。翌1月14日に出演したRKBラジオ『田畑竜介GrooooowUp』で「巨大地震はいつ起きてもおかしくない状況」と話したうえで、30年前の被災者との交流について語った。
阪神の取材先と連絡を取ったその夜に
阪神・淡路大震災(1995年1月17日発生)から、まもなく30年を迎えます。私は当時、毎日新聞の記者でした。現地に取材に入ってお世話になった人たちと、きのう(1月13日)、連絡を取っていました。昨夜、日向灘で地震が発生した後、南海トラフ地震臨時情報(調査中、その後調査終了)が出て、本当にびっくりしました。
地震速報を見て「あ、とうとう!」と身構えたんですが、福岡市内では震度3、揺れがそこまで大きくなかったので、「巨大地震発生ではないのかな」と。いつ大きな地震が起きてもおかしくない状況になっているからです。
でも、昨日のニュースを見ていて、「よくわからない」と思った方も多いんじゃないかなと思うんです。調査が終了して会見が行われましたが、「今回起こった地震は、南海トラフ地震の発生可能性が平常時と比べて相対的に高まったと考えられる現象ではなかった」と説明があったのに、「いつ南海トラフで地震が発生してもおかしくないことに留意をしていただき、日頃からの地震への備えを確実に実施していただきたい」…。「一体どっちなんだ?」と思ったかもしれません。
人間の時間と地学のスケールの違い
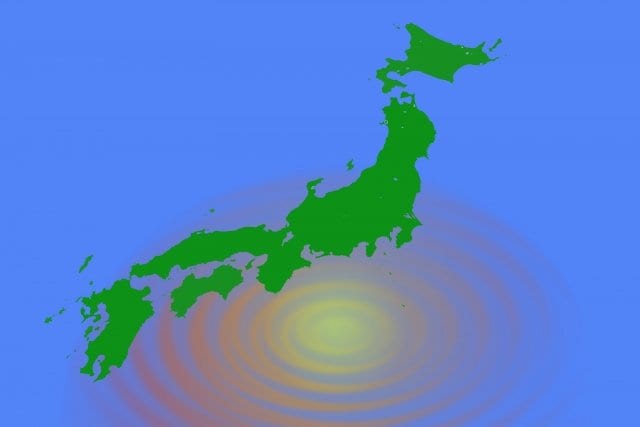
南海トラフ地震は、前回の発生が80年ほど前。戦争中の1944年に「昭和東南海地震」が起き、2年後の1946年に「昭和南海地震」が起きています。その90年前に起きたのが「安政東海地震」(1854年)です。この時は、たった32時間後に「安政南海地震」が起きています。南海トラフは、東側と西側でそれぞれが地震を起こす可能性があって、同時かもしれないし、どちらかが起きた後にどちらかが起きるということもあるのです。
江戸時代は32時間後、昭和の戦争末期には2年間の時間が空いています。地学的に言うと、この差は同じ。”一瞬で起きている”ことなのです。新聞記者として雲仙火山災害を長期間、取材しました(1991~95年)。学会にも入って、研究者と親しく接していました。
噴火は結局5年続いたんですが、ずっと被災地に住み込んで取材したので、私も被災者と同じように疲れていて、「一体いつまで続くんでしょう?」と学者さんに聞いたことがあります。その答えは「1年かもしれないし10年かもしれない」でした。でも、それでは全然心が慰められません。「3年ぐらいかな」とか「8年ぐらいかな」と言ってほしくて質問していたのですが「神戸さん、地学の世界では『1の隣は2、2の隣は3』ではなく、『1の隣は10、10の隣は100』なんです」と言われました。
噴火が1年続くということは、10年続く可能性がある。10年続くということは100年続く可能性がある。3年なのか8年なのかと聞かれてもわからないのです。すごくがっかりした思いになりました。人間の人生を超えてしまうようなスパンで動く地学の世界で、32時間と2年はほぼ同じなんですね。一つの地震が起きてすぐ直後に起きた、と考えていいものなのです。
でも、前回から80年という数字は、実際に起きる可能性が非常に高まっていることを示しています。「平常時と比べて相対的に高まったと考えられる現象ではなかった」と、昨日の地震について発表されましたが、平常時がすでに高すぎる。さらに急激に高まったわけじゃないが、80年をかけて非常に高いところに来ている、ということです。
「南海トラフでは地震が発生してもおかしくない状況に入っている。起きる可能性が非常に高い。起きないわけがない」と考えた方がいいのです。なので、その地域に住んでいる方々はそのつもりでいなければいけないし、日本経済全体が大打撃を受けることは間違いありません。いずれ起きる可能性がある、と考えなければいけないのです。


















