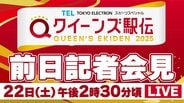世界陸上35km競歩連続メダル(22年オレゴン銀、23年ブダペスト銅)の川野将虎(26、旭化成)が、同種目の世界新をマークした。10月27日に山形県高畠市で行われた日本選手権35km競歩兼全日本競歩高畠で、川野は2時間21分47秒で優勝。日本の競歩は男子20km競歩(1時間16分36秒)の鈴木雄介(36)に続き、五輪&世界陸上実施の競歩2種目で世界記録を保持することになった。
川野は世界記録について「これまでの取り組みが間違っていなかったことを、記録として証明できました」とコメント。だが代表に決まった来年の東京世界陸上に向けて、「これがスタートラインです」と気を引き締める。
高畠の数日後に酒井瑞穂コーチにも加わっていただき、レース内容についてインタビューした。
世界記録の平均ペースから(1km)10秒ペースアップする
――28kmでスパートして勝負を決めましたが、残り7km地点と決めていたのですか?
川野:国際大会で分岐点となることが多いのがラスト7kmあたりで、そこから勝負していくことがメダルを狙って行くためのレースパターンといえると思います。自分もラスト7kmとか、30km手前でスパートして勝負を決めたいと思っていました。パリ五輪を終えてからその準備をしてきました。
――ラスト7km地点より前に、苦しくなった場面はなかったのですか?
川野:予想以上のハイペースで途中苦しい場面もありましたが、それも想定内でした。(6kmから12kmまで)1km4分を切るハイペースになりましたが、そういう展開になることも事前に瑞穂コーチと相談してレースプランも立てていました。世界記録を出せるくらいの準備をしていかないと代表権はつかめないんじゃないかと、瑞穂コーチから言われていましたから。余力があるからスパートをする、のではなく、苦しい中でもスパートする。ここで引き離すんだ、という強い気持ちを持って迷いなく行きました。来年の東京世界陸上のラスト5kmをイメージしながら歩いていました。
――残り7kmの28kmから29kmが3分52秒でした。その前の1kmが4分09秒です。ここまで大きいペースアップをしたことは過去にありますか?
川野:20km競歩では3分40秒台に上げたことがありますが、35km競歩、50km競歩で疲労が大きい中、勝負を決める場面では初めてだと思います。19年に今回と同じ高畠で50km競歩の日本記録(3時間36分45秒)を出した時に、15km以降で(4分04秒に)約10秒上げて、それを2回続けて集団を引き離したことがありましたが。
酒井瑞穂コーチ:19年高畠のときは世界記録が1km平均4分15秒だったので、そのタイムより10秒上げることに挑戦してみました。今回もV.カナイキン(ロシア)の世界最高タイム(非公認で2時間21分31秒)は4分02秒がアベレージなので、3分52秒に上げることを目安にしていたのです。そのくらい上げないと世界陸上の代表権も取れないと考えて、科学的なサポートも受けながら10秒のペースアップが楽にできる準備にこれまでずっと取り組んできました。
川野:パリ五輪の男女混合競歩リレー(岡田久美子=33、富士通=とペアで8位入賞)では、男子は約11kmを2本歩きましたが、そのとき10kmを38分ヒト桁で歩くことができました。パリ五輪に向けてのスピード強化の過程で、35kmの世界記録に対するスピードの余裕度が予想以上につきましたね。高畠ではレース中盤でかなり強い揺さぶりもありましたが、そこでも対応できました。歩型(※)に対して注意は出てしまいましたが、警告はありませんでした。そこも来年の世界陸上につながると思います。
(※)競歩は審判が歩型を判定し、規程の歩型(両足が同時に地面から離れてはならない。また、踏み出した脚が地面についてから垂直になるまで、その脚は曲げてはならない)で歩いていない選手には注意(イエローパドル)が出る。注意されても直らない選手には警告(レッドカード)が出される。3人の審判から警告が出るとペナルティーゾーンで待機(20km競歩は2分、35km競歩は3分30秒)を命じられる。ペナルティーゾーンを出てさらに1枚警告が出ると失格になる。注意や警告が出されると思い切った歩きができなくなるなど、勝負に影響することもある。