両国の関係強化にも関わらず厳しい国境警備・・その訳は「ウイグル民族政策」
一方、カザフスタン側にはどんなメリットがあるのだろうか?今回私は「自由貿易特区」のカザフスタン側の責任者に取材のアポを入れていた。てっきり「自由貿易特区」内にいるのだろうと思っていたが前日にインタビューの場所を再確認すると、なんと国境を越えてカザフスタン側に来いという。
「『自由貿易特区』があるくらいだから、中国側から歩いて簡単にカザフスタン側に行けるのだろう」。気楽に考えていた私だったが国境越えは想像以上に大変だった。まず中国側のバスターミナルから指定されたバスに乗り、中国国境へ→徒歩で移動し、出国手続き→再びバスに乗りカザフスタン国境へ移動→バスを降りて入国手続き→再びバスに乗りカザフスタン側の指定するバスターミナルまで移動と、カザフスタンの地に降り立つまで、なんと5時間近くもかかってしまった。

想定外のバスの旅。しかし、その旅は思いがけず中国とカザフスタンの力関係を考えさせられるものになった。車窓から景色を眺めていると、高層ビルが建ちならぶ中国側の発展ぶりとは対照的にただただ荒野が広がっている。印象的だったのはカザフスタンから中国に向かうトラックの荷台の多くは空っぽだったこと。中国からの輸入品を運ぶためのトラックであることがうかがえる。実際、バスに乗り合わせた中国人男性は中国で買い付けた日用品をカザフスタン側に売る貿易の仕事をしていると話した。「自由貿易特区」でも衣類に日用品に電化製品にとあふれんばかりの中国製品に比べ、カザフスタン側の「売り物」ははちみつとチョコレートくらい。「あまりに貿易不均衡では?」と心配になったが、中国側にももちろんメリットはある。それはカザフスタンの石油、天然ガスや鉱物などの資源だ。そして何度も繰り返すが、中国にとってのカザフスタンの重要性はヨーロッパへの窓口、ということに尽きる。

もうひとつ、バスの旅で気が付いたことがある。異常に厳しい国境管理である。中国とカザフスタンの間には高い鉄条網で囲われた緩衝地帯が延々と設置されている。数キロおきに監視塔もある。国境越えのルートは先ほど記したバスルートのみ。しかもバスを乗り降りする度に国境警備隊の再三にわたるパスポートチェックがあった。中国とカザフスタンの関係は良好なはずではなかったのか?厳しい国境警備の理由。それは、ホルゴスが「新疆ウイグル自治区」にあるからだと、 法政大学の熊倉潤教授は話す。
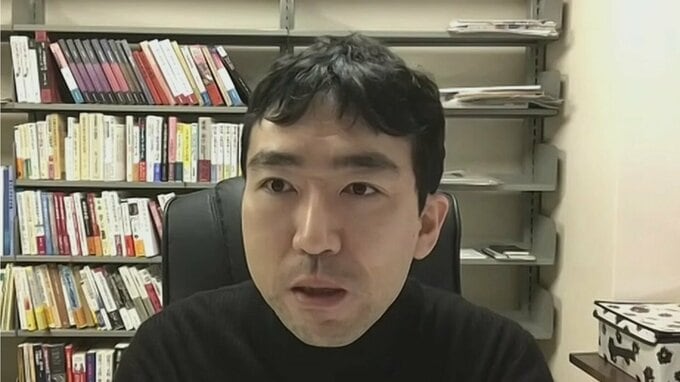
法政大学・熊倉潤 教授
「中国にとってカザフスタンは新疆ウイグル自治区を『統治する』ためにも重要なのです。新疆ウイグル自治区からカザフスタン経由で国外に逃れたウイグルの人たちも多く、また、カザフスタン経由で『ウイグル独立』などの思想の流入を防ぎたい中国にとってカザフスタンは『新疆ウイグル自治区の治安を維持』するためのパートナーとしての意味合いも強いのです」
中国政府に不満をもつウイグルの人たちはカザフスタンなど中央アジアの国々を経由し、国外に亡命してきた。それを防ぐため厳重な国境警備になっているのだという。
近年、新疆ウイグル自治区の人権をめぐり、中国は国際社会から批判を浴び続けているが、ヨーロッパにつながる要衝のカザフスタンに隣接する新疆ウイグル自治区は中国政府にとって絶対に手放せない場所。だからこそ異常なまでの「漢族との同化政策」をとり、「テロ対策」「貧困対策」の名のもと「強制収容所」に人々を送り込み、独立運動を押さえつけるのだ。思いがけずウイグル問題の本質を、厳しい国境警備から垣間見ることになった。
旧ソ連の一員だったカザフスタンをはじめとする中央アジアの国々は、もともとロシアの影響力が強く「ロシアの裏庭」と呼ばれていた。しかし今、大きな変化が起きている。転機となったのは2022年のロシアによるウクライナ侵攻。これにより、中央アジアにおけるロシアの経済的な影響力が低下。その隙を突くように影響力を拡大し始めたのが中国だ。
中国は2023年、「中国・中央アジアサミット」を初めて開催。中央アジアの国々に対し約5000億円の融資と無償援助を行うことを表明した。ヨーロッパへの窓口という地理的な重要性に加えて、中央アジアの国々が持つ石油や天然ガスなど豊富な資源も中国にとって大きな魅力となっている。そしてカザフスタンの最大の貿易相手国は昨年、ついにロシアから中国にとって代わった。















