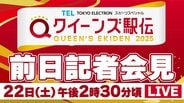「4、5区で抜け出す」ための区間配置は?
学生時代に大活躍した選手が実業団に入社し、足踏みすることは少なくない。だがSUBARUの新人は三浦以外の2人も順調にここまで来ている。
並木は7月に5000mの自己新で走ると、9月の全日本実業団陸上5000mで2組1位。一番速い選手が集まる組ではなかったが、得意ではなかったラストスパートで2位を大きく引き離した。ラスト1周は57秒とチームスタッフも驚くスピードで、他チームの選手たちに強さをしっかりとアピールした。
山本も10000m1組で3位。28分46秒31で自己記録には及ばなかったが「2人とも条件が良いレースなら(10000m)27分台で走ると思います」と奥谷監督。奥谷監督は東日本大会の区間編成を踏まえた上で、レースパターンを「1、2、3区で上位にいて、4、5区で抜け出す展開ができれば勝機はあります」と話す。
全体の距離がニューイヤー駅伝より20km以上短い大会である。1区は3番目に長い区間だが、出遅れはニューイヤー駅伝以上に響く。2区はインターナショナル区間で、SUBARUは強い。そして3区が今駅伝の最長区間。この1、3区をエースの清水歓太(28)と鈴木勝彦(28)、梶谷瑠哉(28)、照井明人(30)の実績組に任せるのか、新人2人を起用するのか。4、5区で抜け出す役目を新人に期待するのか、実績組に任せるのか。
清水は23年日本選手権5000m3位の日本トップランナーで、ニューイヤー駅伝のエース区間でも区間賞争いを期待できる。実績組4人は、東日本大会では区間1~3位を何度も取っている。清水、鈴木、梶谷の5000mシーズンベストは13分30秒台。昨年までの実績でも今季のタイムでも、新人2人を上回る。
奥谷監督の選手起用も注目される。
チームが成長の新たなステージに
3年前、SUBARUがニューイヤー駅伝(22年大会)で2位になったとき、全ての長距離関係者と駅伝ファンが驚愕した。東日本大会は7位で通過したチームである。さらに前年は東日本大会が途中棄権で、ニューイヤー駅伝に出場すらしていなかったのだ。しかし大失敗をしたことで、奥谷監督は思い切った「チーム改革」に着手できた。それが練習メニューと目標設定などを全て、選手に決めさせることだった。社内の重役に選手を直接会わせたりもした。

キャプテンになった梶谷や清水を中心に、選手たちは自主的に行動するようになり、意識が追いつかない選手たちはチームを去った。選手が責任を持って行動することは、自身に厳しくしないとできないことなのだ。
翌23年大会は、「前年の2位がまぐれでないことを証明するために入賞する」ことを目標に掲げ、7位で目標を達成した。しかし24年大会は14位。1区の37位という失敗が響いたが、チーム全体に「同じようにやっていれば」という甘さが見え始めたという。
それを予期していたわけではないが、奥谷監督はスカウトに力を入れていた。役員たちの理解を得るなど、三浦の獲得には会社のバックアップが大きかった。「彼は日本長距離界の宝です。SUBARUのためではなく日本のため」という無私の考え方が、逆に社内の共感を得たようだ。その結果、SUBARUとしては、かつてないほど強力な新人3人が入社した。
そのタイミングで奥谷監督は、東日本実業団駅伝のメンバー選考を厳しくした。実績組は練習でタイムが悪くても、駅伝本番での期待度を理由に起用していたのが東日本大会だった。今年は新人たちの力があり、シーズンを通して好調を維持している。実績組はトラックのタイムが春先は出ていたが、その後は新人に負けるレースもあったり、ピリッとしなかった。メンバーを選ぶための合同練習を何回か行い、チーム内の緊張感が高くなった。
「新人たちはSUBARUに入ることができて喜びを感じています。そんな選手たちがニューイヤー駅伝優勝という明確な目標を持って加わったことで、チーム全体のマインドがまた変わることができました。勢いのある新人と、実績のあるベテラン・中堅選手が融合したチームが、これからのSUBARUになります」
その最初の駅伝が、今回の東日本実業団駅伝となる。そのチームにニューイヤー駅伝では三浦が加わる。三浦は全区間20km超の箱根駅伝に対しては苦手意識があり、今年はまだ本人がストレスを感じない区間に起用する予定だという。
「実業団の駅伝を三浦に肌で感じてもらいたいと思っています。そこで来年以降のチームの進化のために、彼がどういう役割を果たしたいと思うか」
世界で戦う三浦が本当の意味でSUBARUの駅伝に加わったとき、ニューイヤー駅伝優勝が目標になる。
(TEXT by 寺田辰朗 /フリーライター)
※写真は左から山本選手、三浦選手、並木選手