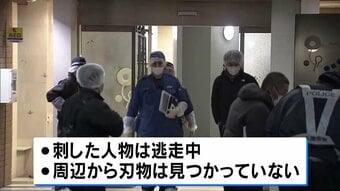「クローズアップ」は「顔」だけではない
岡田 しかし一つ、全然くだらない話ですが、昔のことで記憶がはっきりしていないけれど、確かに影響を受けたと言えば、「悲恋」※という映画がありました。
※「悲恋」1943年のフランス映画(日本公開は1948年)、脚本:ジャン・コクトー、監督:ジャン・ドラノワ、出演:ジャン・マレー、マドレーヌ・ソローニュほか。トリスタンとイゾルデ伝説を現代化した物語。
フランス映画で、ジャン・マレーが主演です。主人公が、自分の好きな女を誘い出して逃げるのです。高い山の上に山小屋があって、そこへ女性を連れて来て「自分が食料を買いに下の町まで行くから、必ずここにいるように」と言って、山を降りるわけです。ところがその間に、女性は連れ戻されてしまう。それを知らずに、彼が食料を持って山へ帰ってくる。
当時の記憶では、山小屋の扉をバーンと開けて中に入って、女性の名前を呼ぶわけです。ところが、普通だとそこで探している所が映るわけじゃないですか。それが全然そうではなくて、周りの連山をバーッとカメラがパーンしていくわけです。そこへ、「ナタリー!」という声だけがかぶる。探している所は全然映らないのに、ダーッと山が映っているのが妙に印象的で非常に頭にあったのです。
だからテレビで実際にやる時に、それが妙に頭にこびりついていて、ああ、これなんじゃないかと。当時は今のように編集が効かないし、山もないし、海もないし、あれなのだけれども。
つまり人間が何かをするという表現ではなくて、何かそこにある物とか手とか足とか、そういうことで表現にプラスアルファを求めたいという意識がすごくあって、手のアップとか、そういうものが非常に多かったわけです。あまり顔を映さないで、手ばかりで芝居をさせるとか。それはその影響みたいな、残影が残っていたのです。何か違うことをやってみたいということで、非常にやったのをよく覚えています。
大山 少し分かったような気がするのは、要するにお芝居を映すというのではない。普通はそうですよね。お芝居をさせて、お芝居をしている顔を撮ってしまうのは普通の演出だけれども、つまりそれがお嫌いというか。
岡田 そうそう。嫌いというか。
大山 乗らないというか。それよりもっと違う表現があるだろうと。
岡田 ああ、そうそう。そういうことですね。
大山 なるほど。それは新しいですよ。
岡田 そのように非常に意識したのです。
大山 それでは中途半端な芝居好きはびっくりしますよ。こういうやり方があるのか、と。ああ、そうか、そうか。少し分かりました。つまり人間の行動だけをとにかくじっと見つめているというようなね。それはやはりテレビの最初は特に、小さなフレームを生かすという意味では有効ですよね。手のアップとか。それは和田さん※のアップ主義とはまた違う話ですね。
※和田勉(わだ・べん<1930~2011>)NHKのディレクター、顔のアップで知られる。