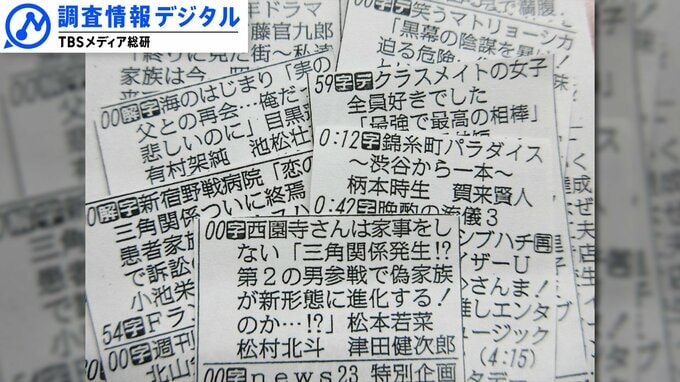2024年7月期のドラマについて、メディア論を専門とする同志社女子大学・影山貴彦教授、ドラマに強いフリーライターの田幸和歌子氏、毎日新聞学芸部の倉田陶子芸能担当デスクの3名が語る。
「虎に翼」の後半は消化不良だった⁉
田幸 まず「虎に翼」(NHK)について。私は脚本の吉田恵里香さんと、実質、原作者に近いぐらいの形で取材や遺族への確認・交渉をやられたNHK解説委員の清永聡さんにお話を伺いましたが、何て大変なドラマだったのかと思います。
視聴者の意見は、前半の絶賛から、中盤以降賛否が分かれました。私もすごくわかります。第1章が完結する河原の場面で日本国憲法を読む。そこまでの完成度が絶賛されるのは当然ですが、以降、扱う差別の問題がどんどん見えにくく、難しいものになっていき、その届き方で賛否が分かれたんだと思います。スタッフもそれは意識していて、現在もまだ続き、解決されていない差別を描く以上、覚悟の上だったと思います。
差別問題はまだ山ほどあって、このドラマにも、一つ一つの差別だけでワンシーズンのドラマが作れるぐらい膨大に入っています。なので「せりふで言うだけ」「何でもかんでも取り上げればいいと思っている」といった消化不良だという指摘もあるわけです。しかし私は、半年という膨大な朝ドラの枠を使って、あらゆる差別、透明化されている人たちを全部書こうという制作者の覚悟に心打たれました。
あと、原爆裁判を扱ったことが大きい。原爆裁判は知らない人がほとんどで、忘れられています。その裁判の判決文を朝ドラで読んだというのは大きな一歩だと思いました。
倉田 私の周りでも、後半ちょっと説教くさいとか、LGBTQや男性同士の同性愛を取り上げたとき、戦後間もない時期に、大っぴらに同性愛者だと公言する人はいないとか、女性同士の同性愛についてほとんど描かれなかったとか、いろいろ個人の思いがあるゆえに、批判的に捉える面もありました。私は、それでも取り上げないよりはいいじゃんと思いましたが。
もっと深く描くこともできたと思いますが、時間の制約がある中で、様々な差別を少しでも示し、視聴者に気づいてほしいという意図が強く感じられました。差別をめぐる問題は、50年、60年たったからといって解決するものじゃない、この先も考え続けていきましょうというメッセージが伝わってきました。
影山 視聴率で言えば、飛びっ切り高い数字を獲得したわけではありません。しかし、今のドラマの作り手が学ぶべき点は、視聴者におもねるだけでなく、それが傲慢になってはいけないけれど、こういう作品、メッセージを伝えたいという思いを届けている、そこがすばらしい。
田幸 伊藤沙莉さんは、今期ナンバーワンですね。役者個人としてだけでなく、座長としての力がすごい。スタッフの方の取材などもしましたが、彼女がエンジンになって他の出演者を引っ張り、現場を動かしているところが相当あったと思います。
どの朝ドラでも言えることですが、後半になるとスケジュールがきつくなります。特に「虎に翼」は後半になって新たなセットが必要になったり、売れっ子の役者さんが多かったりで、非常に厳しいスケジュールだったそうです。
それでもチームが乱れないのは、何といっても伊藤さんがすごいと。あれだけのセリフ量をすぐに覚えて完璧にやる。疲れた顔も一切しない。彼女があれだけやるのだから、我々もといった雰囲気が現場全体にあったと思います。