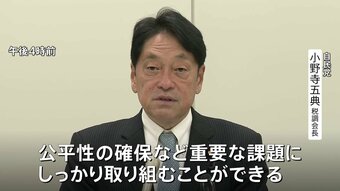生かされなかった“敗北の教訓”
「ノモンハン事件」研究者 ミャグマルスレンさん
「ここは高地なので、敵を見張るには有利でした」

日本軍とソ連軍、モンゴル軍が対峙したハルハ河。高地側がソ連・モンゴル軍。ハルハ河を挟んだ対岸側が日本軍です。

高低差を活かし、日本側の動きを手に取るように把握していたソ連側は高台から砲弾を撃ち込み、戦況を有利に展開しました。さらに…
「ノモンハン事件」研究者 ミャグマルスレンさん
「ソ連軍の戦車や武器の性能が日本軍よりもよかったのです。日本軍はソ連の戦車を倒すため、ガソリンに火をつけた布を長い竹の棒の先につけ、戦車をたたいていました」

最新鋭の戦闘機や戦車を投入したソ連軍と、それに竹の棒で立ち向かった日本軍。ソ連軍の戦力を過小評価していた点も敗因の一つだったといいます。
ノモンハンの敗北で明らかになったこと。それは物資の補給や兵站の貧弱さに加え、装備の近代化の遅れ。そして何より、正確な情報を分析する能力の欠如でした。

「ノモンハン事件」研究者 ミャグマルスレンさん
「もし日本がこの戦いの敗北から教訓を学んでいれば、第2次世界大戦は起きなかったし、広島、長崎に原爆が落とされることもなかっただろうと思うのです」
もし日本がこの敗北を真正面から受け止めていたら、太平洋戦争という無謀な戦いを計画することはなかったのではないか、とミャグマルスレンさんは指摘します。
しかし、日本はノモンハン事件から教訓を得ないまま、2年後、太平洋戦争に突入したのです。
15歳で看護師として戦争に参加したツェリンさん。100歳になった今、若い人たちに伝えたいことがあるといいます。

チィメド・ツェリンさん
「戦争というのは大変悲惨なものです。二度と戦争を起こさないようにしてほしいと伝えたいです」