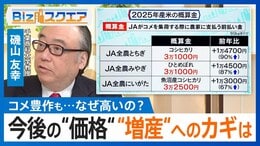植田総裁の任命で、金融正常化に舵
こうした慎重な運び方が、なんとか形になったのが、金融政策の正常化だったと言えるでしょう。
インフレが進行し始めても、「物価2%目標」や「デフレ完全脱却」の旗を降ろさず、「金融緩和」を唱え続けました。
その一方で岸田総理は、自らの手で、日銀総裁に経済学者の植田和男氏を選び、金融正常化に向けた体制を作りました。
その植田総裁は、就任後、1年近くかけて、マイナス金利から脱却。
さらに7月には追加利上げと国債買い入れ減額に踏み切るところまで到達しました。
日本が最も警戒すべき、長期金利の暴騰を起こさずに、異次元緩和を出口に導いたことは、評価されるべきことでしょう。
岸田総理はアベノミクス批判を一言も口にすることなく、アベノミクスの幕引きをしたと言えます。
インフレ対応遅れ、家計負担増
しかし、こうした慎重なやり方が、ポスト・コロナ時代やウクライナ危機によるインフレ時代の到来という、大きな環境変化に機敏に対応できなかったことも事実です。
本来の目標だったはずの2%以上のインフレが、2年以上も続き、実質所得の低下をここまで招いたことは、今や成長の重い足かせとなっています。
金融緩和を続け過ぎたことによる、急速かつ理不尽な円安が、家計や国民経済に与えた弊害は言うに及びません。
国民が物価高に苦しみ、政府自身が物価高対策に何兆円も使っているのに、未だに「デフレ完全脱却」を政策目標に据えていることは滑稽ですらあります。
「デフレ脱却宣言」は、次の政権に持ち越された大きな宿題です。
財政支出拡大に拍車
岸田政権は財政支出拡大に歯止めをかけるどころか、それに拍車もかけました。
時代の要請を受けて、防衛費のGDP比2%への増大、子育て支援の拡大などを次々に決めたものの、巨額の財源を具体的に手当てするところまでは詰め切れず、歳出の見切り発車となりました。
アベノミクスも財政拡大路線ではありましたが、安倍政権は2度にわたる消費税増税を実行しました。
岸田政権は、「新たな恒常的支出には財源対応が必要」という政治の原則をないがしろにしたとも言えるでしょう。
国民負担が重くなっている中で、財政支出のあり方をどう見直すのかは、次の政権に大きな課題として残されたままです。
岸田政権の退陣は、もはやアベノミクスに縛られない経済論戦が可能になったことを意味しています。
新しい指導者を選ぶ過程で、これまでの「しがらみ」から解き放たれた、新しい経済論戦が期待される所以です。
播摩 卓士(BS-TBS「Bizスクエア」メインキャスター)