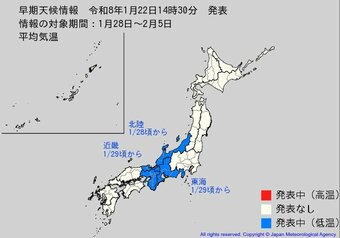「政治的なメッセージ」IOCの対応“少しずつ変化”
藤森キャスター:
ただ、第50条の「政治的なメッセージ」という点について、IOCの対応が少しずつ変わってきているようです。
前回の東京オリンピックの女子サッカーでは、なでしこジャパンの選手たちが人種差別に抗議して片膝をつく行為を見せました
2020年の黒人の暴力や差別に抗議するブラック・ライブズ・マターの運動の高まりが各スポーツ界に広がり、日本だけではなく、イギリス他、各チームで連帯を示すポージングをとりました。
小川キャスター:
容認という形で、対応も少しずつ変わってきているようですね。
日本総研主席研究員 藻谷浩介さん:
1968年のメキシコオリンピック当時は、アメリカで公民権運動が本格化する前でした。黒人差別に抗議した選手が追放されてしまうということが起きました。現在は認められています。
オリンピックは、本来いろんな人が超えて、集まって、戦うものです。本質的に性差別や人種差別とは相いれないじゃないですか。第二次世界大戦時や現在のロシアなど、戦争状態の国だけは参加できません。ですが、それ以外の理由では参加できるべきなので、容認されてきているわけです。
やはりルールというのは、ずっと同じものではなく、少しずつ揺さぶりながら変えていくものです。日本人は真面目なので、一度ルールが定まった以上は真面目に常にフォローしようと思うかもしれないのですが、明らかにおかしいことについては変えていく意識も必要です。
今回の大会で、アフガニスタン出身の選手は「アフガン」(アフガニスタンの女性を解放せよ)と名指しで書いたので、まさに政治的主張になりました。子どもにミサイルが撃ち込まれる様子の刺しゅうのシャツを着た選手ですが、シャツには文字が書かれてなく、ギリギリ認められたんだと思います。
性別、人種、子ども、無実の人が、「戦争だから」といって殺されることは昔はありましたが、もう認められない時代になっていくのではないでしょうか。
あと何年、何十年先かわかりませんが、「戦争するのもダメだよ」というメッセージが認められるオリンピックに向けて、いろんな運動しながらゆっくり変えていくという考えが必要ではないでしょうか。
小川キャスター:
ルールがあるので、沿う・沿わないというのはあると思います。しかし、なぜその選手たちがその行為に及ばなければならなかったのか、その本質から目を背けないということですよね。
日本総研主席研究員 藻谷浩介さん:
この機会を生かさなければいけないと思っている選手の気持ちを大事にしたいですね。