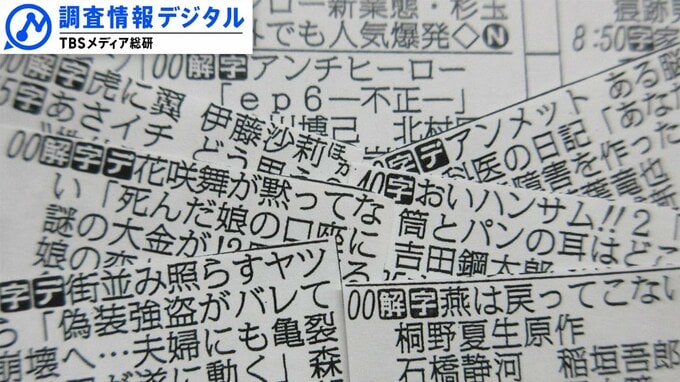2024年4月期のドラマについて、メディア論を専門とする同志社女子大学・影山貴彦教授、ドラマに強いフリーライターの田幸和歌子氏、毎日新聞学芸部の倉田陶子芸能担当デスクの3名が語る。
「虎に翼」の寅子は実は嫌われかねない?
影山 「虎に翼」(NHK) から語りましょう。
倉田 社会の受けとめ方、視聴者への浸透度が、これまでの朝ドラと違うように思います。朝ドラは大体、最初見て、だんだん見なくなるパターンが多いんですが「何十年ぶりに毎朝見てる」「一話も欠かさず見てる」という人が周りにいます。見る側の熱量が違うんです。
初回に、法の下の平等をうたう憲法14条が出てきて、これをテーマに描くというだけで、心魅かれました。今の日本、全ての人が平等であるべきですが、現実には必ずしもそうではないですよね。平等という理想を追い求めてくれる作品なんだろうと思ったんです。
100年前の女性の置かれた状況、親権を持てないとか、職業選択の自由もないとか。主人公の寅子が、そういう状況に対して怒り、あらがって、私たちの代弁者になって「この社会はおかしい」という疑問を呈し、自分の道を切り開いていく過程が痛快です。
私は受験や就職で男女差別を感じたことはなく、働いていて、女性だからちょっとやりにくい面はもちろんあるんですが、機会という意味では平等に与えられています。それは主人公をはじめとする、私の前を生きてきた全ての女性の先輩方が、切り開いてくださった結果で、感謝したいという気持ちです。
田幸 私は今51歳ですが、父が定年退職の年に、大学に進学しました。父は「地元の短大でいいだろう」と言っていましたが、私を応援して、大学に行かせてくれたのは母でした。
だから「虎に翼」で、最初に主人公にとっての壁として立ちはだかるのが、多くの朝ドラだと父親なのに、母親なんだ、珍しいなと思っていたら、実は母親も勉強が好きだったのに諦めざるを得なかったという過去があった。諦めさせられて「スンッ」とせざるを得なかった母親が「地獄の道だよ」と言って送り出してくれたところに感動してしまいました。
このドラマですばらしいのは、トラちゃん(寅子)じゃない人、トラちゃんみたいに言いたいことを言って、やりたいことをやれるわけではなく、諦めさせられたり、言いたいことを飲み込んで「スンッ」とせざるを得ない人、世の中ではそういう人の方が主流ですが、その人たちにスポットを当てているところです。
諦めさせられてきた市井の人々、女性だけじゃなく、正義のために餓死する花岡さんや、国籍が違う方も含めて、我慢をしてきて、いないことにされてきた、いろいろな人たちに光を当てている。
倉田 脚本の吉田恵里香さんの力が大きいと思います。流行語というか、「はて?」とか「スンッ」とか。言葉の響きだけで、どういう状況なのかを表現してしまうワードだけでも、センスがすごい。そして何よりすばらしいのが、まずエンタメ作品として、とてもおもしろい、ということですね。
影山 そこですよね。
倉田 男女の平等など、社会的に重要なテーマを描くことはもちろん大切ですが、それを難しい話で終わらせず、ドラマとしての楽しさに持っていく力を強く感じます。
影山 15分という放送時間を本当に有効に使っていますね。序盤から10分ぐらいすごくシリアスにいったかと思うと、後半でパーッと華やかな明るさに転じたり。伊藤沙莉さんの力も大きいと思います。
田幸 大きいですね。あの役は、ともすれば嫌われかねなくて、身近にいたら面倒くさいという声も結構あります。それも男性から見て面倒なのかというと、意外と女性でも、面倒くさいという人がいるんですよ。
影山 どういうことでしょうね。
田幸 「えっ、何で?」と聞くと、どちらかというと「スンッ」とさせられてきた人たち。それを我慢してきたことに無自覚で、嫌われないように、立場の強い人に逆らわず、いい子にしてきた人たちが、物言う女性を嫌う。闘う女性、はっきり物を言う女性を黙らせてきたのは、男の人だけではなく、黙って我慢してきた女性もそうだという根深い社会構造を感じます。
でも、そのあたりも、伊藤さんが演じることで、やっぱり愛嬌がすごくあって思わず笑ってしまうし、トラちゃんというキャラクターが広く愛されているのは彼女の力が大きいと思います。
影山 緊張の緩和というか、そのバランスがとてもうまい。ヒロインのお父さん、岡部たかしさんが亡くなりそうなときに、石田ゆり子さん演じるお母さんが「まだよ」と言うんですね。ああいうシリアスなシーンで、朝ドラで「まだよ」と言うかな。耳を疑ったというか、うまいなというか。まさに緊張の緩和、すごく高度なことをやっている気がします。