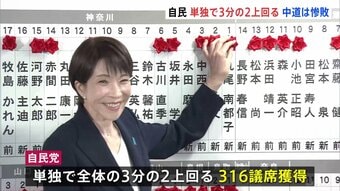たび重なる“改善”が招いた混乱
国が発表する防災に関する情報や市町村が発表する避難に関する情報は、近年の気象災害の激甚化・頻発化等を背景に、「技術の向上」や「改善」という名の下に新設または更新を続けてきた。
例えば避難に関する情報は、現在は「高齢者等避難」「避難指示」「緊急安全確保」だが、2021年5月までは「避難準備・高齢者等避難開始」「避難勧告」「避難指示(緊急)」だった。
さらに時間を遡ると、2016年12月までは「避難準備・高齢者等避難開始」は「避難準備情報」という名称で、「避難指示(緊急)」は「避難指示」。「(緊急)」が付かなかった。
直近で起きた災害の反省や教訓を踏まえて情報の体系や名称を見直すことは大切だが、これだけ短期間にコロコロ変えられては、情報を受ける側はとてもついて行けない。
だから情報を送る側が思い描くような実りある結果には結びつかず、そうしてまた修正が繰り返され…という具合に、大して効果の上がらない“改善”がループ状に延々と続く。
確かに情報の名称は大変重要だ。適当に決めたりするべきではない。
一方で筆者は、情報の名前にいくら手を加えても、どんなに良い名前にしたつもりでも、理解できない人には理解できないし、刺さらない人には刺さらないことは避けられないとも考えている。
一筋縄では行かない「シンプルでわかりやすい」
検討会は、シンプルでわかりやすい〈気象に関する防災情報〉の再構築に向けて、情報体系の見直しや情報名の見直しについて白熱した議論を重ねた。
その席上、気象庁が一般市民や市町村を対象に実施したアンケート、都道府県・報道機関・気象キャスター・ネットメディアから聞き取った意見が紹介されたのだが、結果をひとことで言えば、バラバラだった。
多少の傾向は導き出せたとしても、最大公約数と呼べるものは見出せなかった。わかったのは、そもそも「シンプルでわかりやすい」は人それぞれ違う、という事実だけだった。

情報名よりも重要なこと
だとしたら、情報に良い名前を付けるという行為そのものに限界があるということを十分わきまえた上で最適解を探し出すことが合理的・現実的な選択なのではないか。
どんなに良い名前に思える情報でも、その情報名を脳内でうまく変換・翻訳しないと、いま自分が置かれている状況はどの程度危険なのか、避難行動をとる必要があるのかどうかがわからない…そんな情報は、そもそも防災上有効と言えるだろうか。
検討会の矢守克也座長(京都大学防災研究所教授)は、報告書公表の記者会見で次のように語っている。
「防災気象情報がどういう名称を持っているかはもちろん極めて重要だが、より重要なことは、その情報が人を動かすかどうかに尽きる」
筆者も同感だ。危険な状況にいる人たちに危険度が上昇していることを伝えても、その人たちが避難など必要な行動をとるとは限らない。
災害時にどのような情報提供をすれば人々の行動変容に結びつくのか、防災担当者なら誰もが答えを模索した経験があるだろう。