見つからない、たどり着けない防災情報
この情報をめぐる問題点を、もう一つ指摘しておきたい。
「『顕著な大雨に関する気象情報』が発表されたことはテレビのニュースなどを見てわかるのだが、情報そのものがどうしても見つからない」
このような指摘を、職場の仲間や友人などから複数受けたことがある。
「顕著な大雨に関する気象情報」が発表された場合、筆者は気象庁公式ウェブサイト上で何度も直接確認しているのだが、試しにこの情報について何も知らない前提で、検索サイトに「顕著な大雨に関する気象情報」と入力し調べてみたところ、気象庁サイトの幾つかがヒットし、この情報を解説するページなどは候補として表示されるのに、発表されている情報そのものには簡単にはたどり着けなかった。
ああそうか、と後になって気づいた。見つからないのは「気象情報」だからだ。
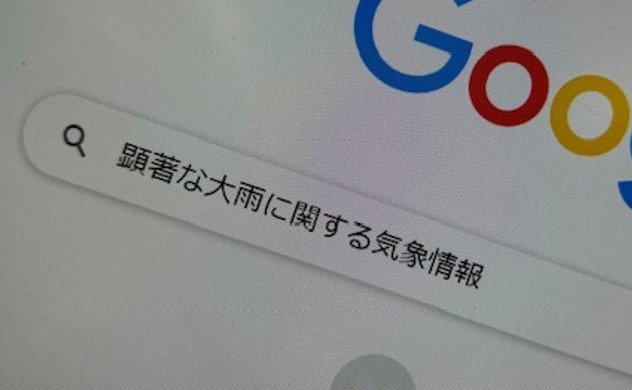
気象庁の「気象情報」は狭義の情報
気象庁は「顕著な大雨に関する気象情報」を、名前のとおり「気象情報」の一種と位置付けている。
「気象情報」と聞いて、皆さんはどのような情報を思い浮かべるだろうか。
〈広く気象や天気にまつわる情報〉というのが、一般の人々の多くが抱くイメージではないかと筆者は想像する。
だとしたら「気象情報」は、だいぶ間口の広い情報ということになる。
ところが、気象庁にとっての「気象情報」はそうではない。
気象庁が定義する「気象情報」とは、「警報・注意報に先立って注意・警戒を呼びかけたり、警報・注意報の発表中に現象の経過、予想、防災上の留意点等を解説したりする」とされている。
ということは、大雨警報や洪水注意報は「気象情報」には該当しない。
では、気象庁のいう「気象情報」とは具体的に何なのか。
その代表例が「全般気象情報」「地方気象情報」「府県気象情報」の3種類だ。
いずれの情報も現在及び今後の気象状況等を解説することを目的としていて、発表対象地域が3種類で異なる。
ざっくり言うと「全般…」は全国を、「地方…」は地方単位を、「府県…」は府県単位をそれぞれ発表対象としている。
そして「顕著な大雨に関する気象情報」もまた、気象庁定義の「気象情報」である以上、解説情報の役割を担っている。
天気や気象によほど関心があるか詳しい人でもない限り、普段接することのない情報の一種だ。
「顕著な…」が「気象情報」という名の解説情報の中に埋没した結果、前面に決して出ることのない控えめな性格の情報になってしまった。基本的にプッシュでは届かない情報になってしまった。
…と原稿を書いている最中の2024年7月14日午前7時47分、長崎県五島地方に「顕著な大雨に関する気象情報」が発表された。
早速、検索サイト経由で情報へのアクセスを試みる。
最上位の検索結果から気象庁の公式ウェブサイトに最近開設された「線状降水帯に関する各種情報」というページに誘導されたが、解説文が延々と続き、目当てのものは見つからない。
結局、「現在発表中の気象情報へ」というリンクをクリックしてようやくたどり着いたが、以前よりいくらか改善されたとはいえ、すぐに探し出せない状況に変わりはない。
筆者はこの情報が「気象情報」に分類されていることをあらかじめ知っていたから、今までPCやスマートフォンから情報そのものを比較的簡単に見つけ出すことができていたに過ぎない。















