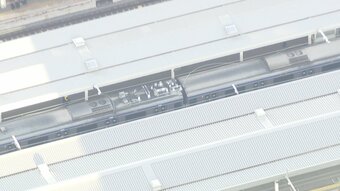政治にかかるお金 国民理解得るには説明する不断の努力を

ーお金がかからない政治という論点でいくと、議員ごとに選挙区の広さも全く違うので、事務所費やスタッフの人数に制限を設けるべきと言う方もいるが
いわゆる出口規制という問題ですけど、絶対ありえない制度だとは私も思いません。
例えば選挙区の広さは違うんだという反論に対しては、公設秘書3人まで国からわれわれ支援をいただいていますけど、その選挙区の広さに合わせて公設秘書の人数を変えるべきじゃないかみたいな話になりますから、少なくともそこではないんだと思うんです。
しかしながら一方であるべき姿っていうのは、政治資金とは何ですかということを共有していくことというのは重要だと思うんですよね。
そこがない限り基本的に絞る方向、縛る方向にしかいきませんから。何のためにわれわれがいるのか、少なくとも議員に初めて当選したときには、全員間違いなく国民のために汗をかこうと思ったはずなんですよ。私は今も思っていますよ。
皆さんも引き続き今も思っていると信じていますけど、不正が起きるというのはちょっと外れているじゃないですか。不正をすることを普通は思わないはずですから、そういったものが出てくる限り、悪になっちゃうんですよね。悪になると規制をすると、縛る絞るという方向になりますから、本来であるところの政治家というのが、国のためにやっているんだということ、国民のためにやっているんだと。
それをどう支えられるのかという方向の議論というのが、あわせてセットじゃないと間違いなく永遠に縛る方向になりますから。そうすると究極的には日本という民主主義国家が非常に国際社会の中で脆弱な国になるわけです。
例えばフェイクニュースとか多いですけども、これに苦しんでいる国もあります。
こういった民主主義の中である種のポピュリズムに非常に弱い国になるということも考えられますから、そういうところもあわせて考えていくべきだと思います。
結論を申し上げれば出口の規制というのはありうる、選択肢の1つだと思いますけれども、どこで縛るのか、これから結構いろんなハードルはあると思います。
ー最終的に大野議員が目指す政治改革の完成形、イメージはあるか
最終ゴールは、私は民主主義というものを、民衆がどういう理想像なんですかというところに行き着くと思うんですよ。それは政治を縛る方向の、どうせ政治家は余計なことを考える人種だからきっちりと絞り上げろ、そういう方向がいいのか。あるいはそうじゃなくて、一定の不正を許さない制度はしっかりと作るけれども、何をやっているか、どういう活動をしているのか、ここが理解されれば、全然いいんだと思うんですよ。私もお金、(政治資金収支報告書で)全部公開を普通しているじゃないですか。
これについて、これ使うな、あれ使うなと指摘を受けたことはありません。もちろん詳細を調べたら、これはなんだと言われるかもしれませんけれども、結局、今回の事件も、金額も何千万という形で踊りましたけれども、どういうふうに何に使ったのっていうのがほとんど説明を聞いたことは私もないわけで。仮に、実はこういう政策を立案するために、こういうふうに使って、例えば国が、シンクタンクやコンサルに調査依頼をかけると1000万円単位で出ていくわけですよね。
国ができることをわれわれ議会としても、やっぱりやりたくなるのは当然なんですけれども、さすがに何千万単位っていうのは費用がないわけですよ。
だけどそういうのに使っていましたといったら、「ああそうなんだ」と思うと思う。
その後不正をやったかどうかということは別の話になります。少なくともなるほど、と思うはずなんです。
だから理解されるポイントは1つ。説明できること。
人間の心理って原理原則というのは比較的シンプルで、信頼できるかってやっぱり説明聞いてなるほどと思うことじゃないですか。ここが1番の目的、目標なんですよ。
だから、決してこの制度を作ったから、こういう制度が目標だというのはあり得なくて、それこそ常に努力をしていく、不断の努力と言いますけど、ここにはすごく重い意味合いが私はあると思っていて、どんなことであるにせよ、説明できるということを常にやっていくと。
ちょっと余談になるかもしれませんが、通常、原則主義って例えばハードなルール、これをやってはならぬみたいなものがあって、ここを超えると違反で捕まるみたいな世界ですよね。
もう1つがよく企業統治などに用いられる原則主義というのは一応ルール、ラインは定めるんですけど、それに対して遵守できるんだったら遵守して、遵守できないんだったら説明しなさいというルールになっているんですよ。
実は政治も最近ガバナンスコードというのを入れるようになりました。問題は、この原則主義の説明の仕方が極めてわかりにくいんですよ。
例えば、政治家の定年制の議論があるじゃないですか。前からあるわけです。原則77歳となっているんですけど、原則ということは必ず説明責任を負うはずなんです。
それで、「いやいやこの人は立派だから」という、こういう一言で片づいてしまっている部分があるんですね。説明というものに基準を定めない限り、私は国民の皆さんが説明を聞いてなるほどと、説明が十分だったと思うとは思えないんです。
ただ真剣に説明を繰り返しているのになかなか説明が十分じゃない、そういった場合はおそらく前提が合っていないのだと思います。ポイントは説明です。