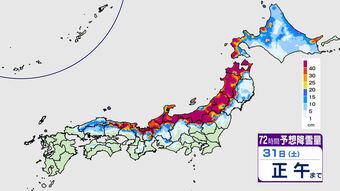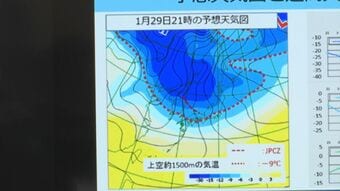「家庭で毎食きちんと手の込んだ料理を作るようになったのは、高度経済成長を経て安定期になって、日本社会が豊かになってからのこと。それまでの自営業や農業中心の社会だった頃は、家庭の中で妻は内職や家業の手伝いという形で働くことが多かったんです」

夫が「会社勤め」、妻が「専業主婦」という、一般的にイメージされる“昭和の家庭像”は、1970年代以降に一般化したもの。
女性は結婚後夫を支え、家事・育児に専念するべきという「性別役割分業」意識が強まり、専業主婦が増加しました。
1985年には男女雇用機会均等法が制定され、女性の社会進出も叫ばれるようになりましたが…
「女性も徐々に外に働きに出るようになりますが、今度は『新・性別役割分業』という言葉が出てきた。男性は仕事、女性は仕事も家事もするというような分業になって、女性への過重負担が問題になってきたんです」