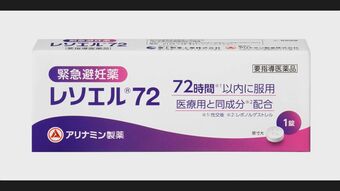強まる「台湾人」意識、その根底にあるのは「民主主義」
「この協定によって台湾経済が中国に浸食され、台湾と中国はもともと同じ家族なのだ、という空気が社会に醸成されるのではないか。それは台湾にとって非常に危険だと思いました」
同世代の大学生が立法院に突入する映像を見て、運動への参加を決めたという陳さん(35)。当時、大学院生だった。

中国という世界第2位の経済大国と隣り合わせの台湾。常に、その巨大な経済的吸引力との距離感、が台湾の課題になっている。台湾が生き残るためには中国経済の勢いを取り込まない手はない、と中国とのビジネスチャンスに期待する声も多い。実際、国民党が推し進めた「サービス貿易協定」は、こうした期待を反映したものだった。しかし、陳さんは当時、「中国が台湾に経済的メリットをもたらすのは、いつか台湾を統一するために他ならない」と危機感を持ったという。
そのような考えに至ったのは、陳さんたちの世代は上の世代とは違うアイデンティティを持っていたからではないか、と分析する。
陳さん
「私たちの両親は国民党がつくった教科書で中国のことを中心に学んでいましたが、私たち、戒厳令が解かれて以降に生まれた世代は、台湾自身の歴史や文化を学校で習い始めた世代です」
中国共産党との戦いに敗れ、台湾に逃れてきた蔣介石率いる国民党は戒厳令を敷き、多くの人を政治犯として逮捕、弾圧したほか、言論の自由も厳しく制限した。現在30代となっている陳さんたち「ひまわり学生運動」世代は、戒厳令が解除された1987年以降に生まれ育った世代。言論の自由、政治的自由を享受して育ったこの世代は、自らを中国人ではなく、生まれながらにして台湾人だと考える人が多く、「天然独」とも呼ばれる。「ひまわり学生運動」は、そんな「台湾人」としての意識を再確認させられるものだったという。
陳さん
「あの運動によって、私たちは『中国の台湾人』になりたくない、『台湾人』になりたい、という考えがさらに強まりました」
「サービス貿易協定」が問いかけた「中国との距離感をどうするか」という問題を通じ、「台湾人」としてのアイデンティティをさらに強固なものにしたという陳さん。

さらに学生同士で議論をする中で、「民主主義」こそが台湾の大切な価値観であり、自分たちのアイデンティティの根底にあるものだと気がついたという。
陳さん
「台湾には選挙があり、自分たちの一票で総統を選ぶことができます。中国のように任期無制限の主席を選ぶようにはなりたくないと思いました」
中国と台湾を分けるもの。それは「民主主義」ではないか。陳さんはそう考えている。
民主化して37年。民主主義国家としてはまだ歴史が浅い台湾ではあるが、市民の政治参加意識はとても高い。今年1月の総統選の投票率は71%。前回、2020年の総統選の20代の投票率は7割を超えた。選挙集会でも、若者の参加が目立つ。なぜ、台湾の若者は、政治参加に熱心なのだろうか?陳さんからは、おもいがけない返事が返ってきた。
陳さん
「私たちは実は日本がとても羨ましいのです。なぜなら、日本は独立した主権国家であり、それが脅かされる日は来ないでしょう。でも、台湾は(中国によって)いつか主権が脅かされるかも知れない。投票によって私たちの未来が決まってしまう、と思うからこそ、政治意識が高くならざるを得ないのです」
たしかに、常に中国による軍事的政治的脅威にさらされている台湾の人たちにとって、どのような政権を選択するかは、自らの生活や将来に直結する死活問題だ。
現在子育て中の陳さん。台湾が台湾らしくあるための重要な価値観である「民主主義」を、子供の世代まで守っていきたいと願っている。
「自分の子どもは、自由な言論が保障された、民主主義のなかで育ってほしいと思っています」
ひまわり世代が感じる次世代への「不安」
「ひまわり学生運動」から10年。この間、中国と距離を置く民進党政権が8年にわたり続いた。その中で育った今の20代の若者たちは「ひまわり学生運動」世代とはまた違った価値観を持っているという。

当時、大学一年生で「ひまわり学生運動」に参加した王さん(34)は、今の若者たちをこう評した。
「いまの学生たちは民主主義が当然の社会で子供時代を過ごし、民主主義は消えてなくなることなどなく、そこに当たり前にあるものだ、と思っています」
「私たちは国民党政権を経験したからこそ、中国の脅威を感じるのです」
民進党政権下で育った今の20代の若者たちは、「中国の脅威」や「中国との距離感」といった問題よりも「若者にも家を買えるようにして欲しい」「就職できるよう経済を良くしてほしい」など、自分たちの身の回りのことへの関心が高いという。
そのため、王さんは選挙のたび、いつも不安な気持ちになるという。
「私たちの世代が抱える危機感を下の世代に伝え続け、民主主義はそこにあるものではなくて、絶えず勝ち取らなければならないということを伝え続けたいのです」
しかし、そんな彼の不安を打ち消すような事態が再び、台湾立法院を舞台に起きることになる。