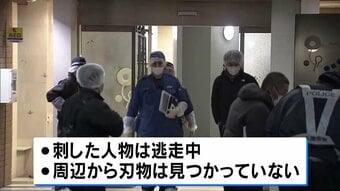先島地域での国民保護に関する検討状況と論点
武力攻撃事態等に伴う先島地域での国民保護については、域外への住民避難を中心に、沖縄県を含む九州各県および国や関係機関による検討が様々な形で進められてきている。
これらの検討では、武力攻撃予測事態の段階で先島地域外へと避難することを前提に、主な避難手段となる航空便の運用(運行ダイヤの組み方や空港でのオペレーション、避難者の誘導などの具体的な方法)や、受け入れ先での初期対応、避難そのものが命のリスクとなる人の数の把握と避難方法といった技術的検討が行われ、成果が蓄積されている。
他方、図に示すように、ウクライナ戦争などでも散見された残留者の保護などを含めた避難フロー全体を見渡すと、そこには様々な課題が存在していることがわかる。

この避難フローの中でも「早期避難の追求」は特に重要である。実際の被害が発生する以前に危険な地域から避難することは、防災においても基本とされることであり、少なくとも人命被害を極小化するための最も基本的な方法だからである。以下では、この早期避難をめぐる論点を中心に論じていく。
早期避難を実現するためには、武力攻撃予測事態などの認定の迅速化が必要となる。しかし、武力攻撃に関する事態認定は、日本側から状況をエスカレートさせることになりかねない危険性がある。
早期避難の実現とエスカレーション抑制を両立するために重要となるのが、国内外との戦略的コミュニケーションである。それは、制約の多い島しょ地域での住民避難の特殊性を説明し、軍事的な活動を含めた日本側の事態への対応について高い透明性をもって示すことで国際社会の支持を勝ち得る努力を指すものである。
同時に、避難を支える民間事業者などとのリスクコミュニケーションも必要となる。なぜなら、大幅に進展している避難手段に関する技術的検討と異なり、避難時の安全をめぐる議論は、実務担当者のレベルで結論が出るものではなく、ハイレベルでのリスクコミュニケーションが不可欠だからである。
この点、現在の国民保護の枠組みでは、防災における「中央防災会議」に相当するような、首相をはじめとする政府首脳部と指定公共機関の代表や有識者が議論を交わせる場が制度上存在していない点は大きな課題と言える。
また、たとえ政府が早期の事態認定を行えたとしても、それだけで住民が避難できるわけではない。
太平洋戦争の際に南洋諸島や沖縄からの住民避難が進まなかった理由の一つとして挙げられているものに、避難先での生活保障があった。この点を踏まえれば、具体的被害が発生していない武力攻撃予測事態の段階で避難を開始・完了させるためには、避難以降の生活の見通しについて具体的なイメージを提示できるよう中長期的な観点からの準備が不可欠である。
そして、中長期的に必要となる支援は既存の制度だけでは提供できないことも想定される。そのため、既存制度の拡張や新規制度の導入などを含めた柔軟な対応を想定しておく必要がある。
これは極めて多岐にわたる話題だが、一例を挙げるとすれば、福島第一原子力発電所事故の際に見られた特例事務の導入(就学案内など本来は住民票に紐づいた行政サービスを住民票の移転がなくとも避難先自治体で提供できるようにした措置。福島原発事故では法を新規に制定して実施した。)などが一案として考えられる。
また、政府は2024年3月末に、先島地域での設置を前提とした緊急一時避難施設に関する技術的なガイドラインを示したが、武力攻撃が発生してしまった地域に何らかの事情で残留している住民への保護についての検討は端緒についたばかりであり、避難施設の整備のあり方などハード面での議論の深化とともに、戦闘地域下の残留民保護や避難のための赤十字国際委員会(ICRC)などの国際機関の連携強化や、人道回廊を含む「文民保護のための特別地帯及び地区」を設定する際の具体的な手順などソフト面での対策についても検討を促進していく必要がある。
国際機関との連携について補足すると、ウクライナ戦争でも見られた「人道回廊」のような避難経路の確立とこれを利用した避難オペレーションの執行において、国際機関、特に現場での執行にあたることが多いICRCの果たす役割は大きいが、ICRCによる人道支援を円滑に行うには、その中立性を関係国が担保する必要がある。
ウクライナ戦争に関しては、ロシアとウクライナはどちらも90年代に「本部協定」(Headquarters Agreement)を締結し、ICRCに対して国際機関としての「特権と免除」を認めていたが、日本政府は同様の取り決めをICRC側と締結しておらず早急な措置が必要となっている。