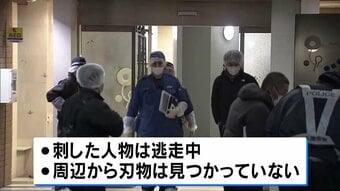各種事態と「台湾有事」との関係と国民保護措置
国民保護法の適用は、「武力攻撃事態:武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態」または「武力攻撃予測事態:武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態」あるいは「緊急対処事態:武力攻撃に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態または当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態で、国家として緊急に対処することが必要な事態」のいずれかの認定がなされていることが前提となっている。
上の定義から明らかなように、台湾有事それ自身は国民保護法が適用される3つの事態のいずれにも当てはまらない。つまり、台湾有事の発生を直接の理由として国民保護措置をとることはできないことになる。
それゆえ、「台湾有事が日本において国民保護措置を必要とする状況になるかどうか」は「台湾有事への日本の関わり方が、結果として日本をして武力攻撃事態や武力攻撃予測事態を認定せざるを得ない状況となるのか」にかかっている。
それは、一面では、「発生した台湾有事が現象として日本にどのような影響を与えるのか」という議論なのだが、もう一つの側面として、「発生した台湾有事に対する日本の対応が、日本への武力攻撃の正当性を主張できるものとして有事の相手側(端的には中国)に認識されるかどうか」という議論でもある。
この観点から具体的に考えうるシナリオの一例としては、日本が台湾をめぐる有事を「重要影響事態:そのまま放置すれば日本に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等日本の平和及び安全に重要な影響を与える事態」、あるいは「存立危機事態:日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」と認定することで、相手側からは日本が台湾有事における一方の当事者と見做され、まさしくそれゆえに武力攻撃が生起する危険性に備えて同時並行的に武力攻撃予測事態を認定する必要に迫られる、といったものが挙げられる。
日本最西端にある与那国島からわずか111kmしか離れていない台湾で軍事的な緊急事態が発生した場合、それが日本になんの影響も及ぼさないとは考えられず、日本政府にも相応の対応が求められよう。だからこそ、「台湾有事は我が国有事」という言葉は一つの見識ではある。
しかし、上に示した制度の複雑な関係性を考えれば、この言葉は、近隣地域で発生した緊急事態への関与の結果として日本国内での被害発生を甘受せざるを得ないという現実を示すものでもある。だとすれば、安易にこの言葉を口にする行為は、国土と社会に対するある種の無責任さを示しているとも言える。
とはいえ、ウクライナ戦争直前の日本の論調が戦争の発生を予期し得なかったように、台湾有事を含めた日本周辺での武力紛争が我々の予測や認識を超えて不意に発生し、日本がその当事者となってしまう可能性を否定することはできない。
だからこそ、国民保護は、台湾有事やその他有事の可能性の高低とは関係なく平素から不断に検討しておく必要がある。かかる観点から、ひとまずは台湾有事を背景として国民保護を考える際の課題を検討していく。