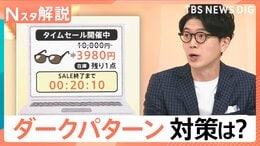専門家 “引き渡しギリギリで解体”「一般的にはないこと」

不動産コンサルタント 長嶋修さん:
この業界に30年以上いますが、このような形で解体になる事例は初めて見ましたし、実際にこれまで無かったように思います。普通は建築確認を出して通れば合法なので、そのまま進みます。
慣行として住民説明会を開いて、眺望や景観に配慮する“妥協点”を探ることはありますが、一定程度行った後は「ここで終わりです」と前に進むというのが通常です。
引き渡しギリギリに「やっぱり解体します」というのは一般的にはないことだと思います。
井上貴博キャスター:
積水ハウスの判断なので仕方ないとは思いますが、これが前例となって、反対運動が起きている全国の他の地域で「積水ハウスは解体してくれたよ」という交渉材料になってしまうのではないでしょうか。
他の建設会社も気を揉んでいると思うので、「富士山が見えないこと」だけが要因なのか、他の要因があるのであれば発表してもらいたいです。そうでないと全てが交渉材料になってしまう気がします。
不動産コンサルタント 長嶋修さん:
全国で建設反対運動はたくさんあると思います。今後、反対運動が起きたときに、今回の件が前例となってしまうのではないかと業界として気を揉んでいるところはあると思います。
今回の積水ハウスは“解体”で片が付いて良かったのかもしれませんが、業界全体に与える影響は非常に大きいと思います。同じようなことが各地で勃発する可能性がないとは言えません。

ホラン千秋キャスター:
「景観を損ねるから建てないで」ということは色々な地域であるだろうと思いますが、国立市の今回の件では何をもって「周囲への影響がかなりあった」と判断をしたのでしょうか。
1~2人ではなく、一定程度の人に対して「景観を損ねるという不利益を被るから解体します」ということなのか…線引きが難しいように感じます。
不動産コンサルタント 長嶋修さん:
法律も条例も、例えば「富士山が何%見える」というような細かいところまでは書いていませんので、双方の話し合いなど、トータルで判断していくことになってしまいます。
今回のケースは「景観を損ねた」ということだけではなく、事業全体の収支なども関係しているのかもしれません。
今回のマンションは全18戸のすべてが売れていたわけではないようです。引き渡し後も販売をするとなれば、一定程度の値引きをして販売する可能性もありますから、全体として黒字を保てるのかということも判断材料のひとつだったかもしれません。
また、もしも訴訟が起きた場合、裁判が起きているマンションを買ってくれる人がいるのかといった点も含めて、トータルの事業としての判断があったのだと思います。
==========
<プロフィール>
長嶋修さん
不動産コンサルタント
個人向け不動産購入の専門家