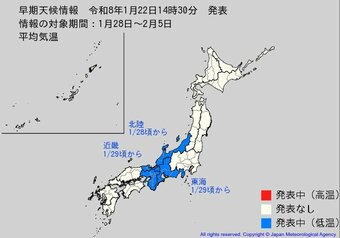深夜まで記者対応
人事異動に伴い、熊﨑は捜査体制を立て直した。1997年4月からはこれまでの「機動班」を、「特殊・直告班」に組み入れ、「特殊・直告班」を「1班」と「2班」に分けることにした。その「1班」で「野村・第一勧銀・総会屋事件」を統括する副部長は、泉井事件に続いて笠間治雄が担った。「2班」の副部長・山本修三は当面「大和証券」など捜査にあたり、のちに笠間の「1班」引き継いで「大蔵省汚職」の陣頭指揮を執った。
副部長以下は事件全体の「主任検事」に井内顕策、「総会屋」の最大の資金源となった「第一勧銀捜査班」の班長に大鶴基成を据えた。加えて、東京高検管内の地検からの応援検事を30人を投入し、証拠物の分析と参考人の取り調べを担当させた。さらに野村証券が国会議員などの特別顧客、VIP口座を優遇していた実態を調べるために、「SEC」から帰任した粂原研二を班長とする「政界ルート特命班」を設けた。
司法記者クラブのP担(検察担当記者)への対応は原則、特捜部長と副部長があたることになっている。検察は、記者が幹部以外のヒラ検事や検察事務官に接触することを禁止しており、ヒラ検事との接触が幹部に伝わった場合、そのメディアは「出入り禁止」となり、ペナルティの段階によって、次席検事の会見や特捜幹部への取材が禁止となる。もっとも、独自ルートを持っている記者には「出入り禁止」は何の効果もない。
司法記者が特捜検事との接触を試みる時間帯は主に出勤時と帰宅時だった。夜は外から特捜部の窓の灯りが消えるのを確認して、検事宅に向かうのだ。身柄を持っている場合などは連日、東京拘置所で長い取り調べを終えて終電以降に帰宅する。深夜に記者が自宅周辺で待つと近隣の迷惑にもなりかねないため、熊﨑は当時、よく世田谷区砧の自宅近くのスナックを使って記者対応をしていた。
当時、最も若手のP担(検察担当)だった秌場聖治記者(TBS)は振り返る。
「熊さんと番記者が行くのはだいたい世田谷通りから少し入った日大商学部の近くにあった『セカンドハウス』というスナックだった。近所の常連がカラオケで美空ひばりの「車屋さん」を歌うような気さくな店で、20人も入れば一杯だった。
夜が深まると、熊さんが『そろそろイチイチやるか』と言って、ようやく店内で、各社数分ずつの『持ち時間』で個別対応に応じてくれた。熊さんはときどき特捜部の佐々木善三さんらにも声を掛けて、店に連れてきた。新聞社は常に朝刊締め切りの『午前1時半』を意識していたが、それを過ぎることも普通だった」
秌場たち番記者は当時流行していたSMAPの「ダイナマイト」や「青いイナズマ」、安室奈美恵の「Don’t Wanna Cry」などをよく選曲した。それらの歌詞を、特捜部がその時期に、まさに内偵捜査を進めている事件にひっかけた「替え歌」にして歌い、熊﨑の反応を見た。
その時の熊﨑の微妙なリアクション、言い回しの変化をとらえ、捜査の進捗状況や強制捜査着手のタイミングの糸口を探ったのである。
熊﨑は「現場が組織全体を支えている。常に現場がどう考えているのかを知りたい」との思いから、現場の特捜検事と積極的に意思疎通を図った。そうした現場との結びつき、現場に入り込んで都合の悪いことも聞くというやり方は、のちにプロ野球のコミッショナーとなっても変わらなかった。折に触れて部下に「一杯いくか」に声を掛け、連れていく店が東京・渋谷の行きつけのスナック「洋子」だった。熊﨑はかつてこう話していた。
「いい仕事をした検事は、ほおっておいても機嫌がいいから大丈夫。調べが不足しているとか、ブツ読みが進んでいない部下と飲みにいく」
熊﨑の所在がわからないとき、筆者は「洋子」に向かい、店から出てくるのを待って接触した。事件の節目には、店内から熊﨑が「同期の桜」を歌う声が聞こえてきた。若者が集まる華やかな渋谷のセンター街から、細い通りを入った路地にあった。なぜその店かと言えば、もともと店のママと、かつて特捜部にもいたS検事(20期)(のちに法務省矯正局長、広島高検検事長、高松高検検事長)が福岡出身で同郷だったことから紹介されたという。
主任検事だった井内顕策(30期)も当時を懐かしむ。
「夜、霞が関の検察庁からタクシーで渋谷の『洋子』に向かうときは、ちょうど当時住んでいた麹町の官舎の前を通りすぎていたので、『ここで降りたらそのまま帰宅できるのに』とよく思いながら付き合った。熊さんは元気だから、午前2時や3時まで飲むこともあったが、そうした熊さんの部下への気配り、特捜部の風通しを良くしたいという配慮が身に染みた」
ゆるぎない結束を固めながら、その後1年以上にわたり、特捜部は法務省や全国の地検などからも応援検事を投入し、前例のない規模の捜査体制を整え、「4大証券・第一勧銀、総会屋事件」「大蔵省接待汚職」という「聖域」に切り込んでいく。
「応援検事は熊さんがある程度、実力や評判を知っていて呼んだ検事が多かった。第一勧銀ルートの葉玉匡美さん(45期)や奥村淳一さん(36期)、日銀接待ルートの長澤格さん(46期)など優秀な人が多かった」(元特捜検事)
副部長だった山本修三(28期)は振り返る。
「5月の段階で、応援検事含めてロッキード事件並みの体制と言われたが、9月以降「秋の陣」に向けて副部長も4人に増員し、野村証券に続いて、山一証券、大和証券、日興証券への4大証券着手の頃はさらも応援検事を増やし、検事は70人近くに拡大した。特捜部だけで東京地検全体よりも人数が多いじゃないか、とよく言われた。かといって、応援検事をいつまでも引っ張っておくわけにはいかないので、どこで解除するのか、捜査の進捗状況を見ながら判断した」
「立件するのは野村証券だけの一罰百戒でいいんじゃないかという検察幹部もいたが、4大証券すべてに不正の証拠があるのにやらないのは不公平感が残るとの判断だったと思う」(山本副部長・現弁護士)