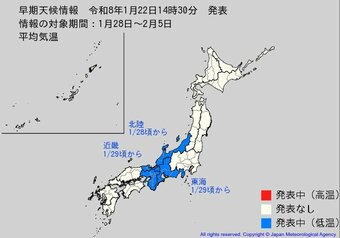「いかなる圧力にも左右されてはならない」
粂原は「オーソドックスな捜査」の重要性を指摘する。
「初めに着手する事件となった革手錠重傷事件について、最高検や高検など上級庁の幹部の中には、『こんなものは業務上過失致傷だろう』などと反対する人もいたが、そういう上司の言うことに従う必要はなく、もちろん、その幹部も説得した上で、徹底した捜査を進めることで、革手錠事件と放水死亡事件のいずれも立件することができた。
案の定、刑務所側の組織的な抵抗を受けたが、一件一件「着実に任意捜査」を尽くした上で、その後「強制捜査に移行」するという、オーソドックスな捜査手順を踏むことによって真相にたどり着いたと思っている」
この事件をきっかけに、法律も改正された。約100年前の明治時代に制定以来、一度も改正されることなく、現実にそぐわなくなっていた「監獄法」が廃止され、代わって受刑者の人権尊重と処遇改善を大きな目的とした「刑事収容施設法」が成立したのであった。「受刑者にも人権がある」という当たり前の考え方が導入され、たとえ受刑者が指示に従わない場合でも、暴力に頼ることは許されなくなった。
「総会屋への利益供与事件も名古屋刑務所事件も、うやむやなまま終わらせることは、不可能ではなかったと思うし、それを望む人も大勢いたと思うが、検事は『法と証拠にのみ』基づいて仕事をしなければならず、いかなる圧力にも左右されてはならない。
また、少し頑張れば証拠が収集できるのに、難しいとか面倒だといって逃げ出してはならない」(粂原)
総会屋事件に話を戻す。1996年の夏から秋にかけて、粂原ら「SEC」のチームは、野村証券が小池隆一の実弟の口座「小甚ビルディング」に、利益を付け替えていた事実をつかみ、野村証券の関係者への「質問調査」に乗り出した。
しかし、野村証券の「徹底抗戦」は依然として続き、関係者からは「利益提供」の事実関係すら供述を得られない状態で、1996年の年末を迎えることになる。
この頃になると司法記者クラブの報道各社も「SEC」が特捜部と連絡を取り合いながら、野村証券の関係者から事情を聴いていることに気づきはじめ、水面下で取材合戦がはじまっていた。意外にも第一報の口火を切ったのは全国紙やテレビではなく、ブロック紙の「北海道新聞」だった。
(つづく)
TBSテレビ情報制作局兼報道局
「THE TIME,」プロデューサー
岩花 光
◼参考文献
司法大観「法務省の部」法曹会、1996年版
司法制度改革審議会第56回議事録、2001年