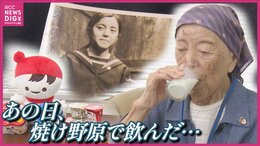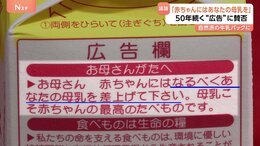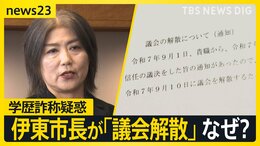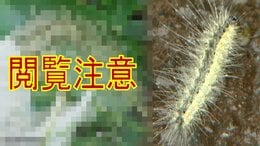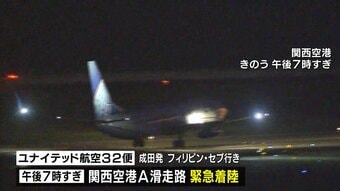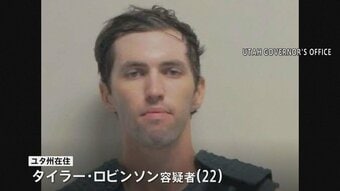ギリギリの経験がパニックを防ぐ 身近なところからアクションを
――体験学習というと、小学校のときに海で3キロ立ち泳ぎをしろと言われて。何のためにやっているのかって。
野口健氏:
それは、いざというときにパニックにならないんですよ。ギリギリの経験をするじゃないですか。それを何度かやっていると、本当にピンチのときにパニックにならないんです。娘が中学校のときにキリマンジャロに登ってみたいって言うので、すぐ連れて行っても多分登れたんですけど、それじゃ意味がないんで、2年かけようと。国内で合宿を2人で2年かけてしたんです。
雨の日とか、天気の悪い日にあえて行くんです。ザンザン降りの中を15時間くらい歩かせるんです。やっぱり肉体的苦痛とかストレスとかあるじゃないですか、濡れるとか寒いとか。最初泣くんですけど、それを積み重ねていくと、あのときに比べたら今日はまだいけるとか、自分の限界を知ると、ちょっとスピードを落とそうとか、人間って苦痛を体で定期的に経験しておくと、パニックにならないんですよね。だから、ある程度苦痛を与えるっていうのは大事なんです。
キリマンジャロに行ったとき、最後すごい吹雪になったんです。山頂まであと残り1時間ぐらいでした。行けるか行けないかギリギリだなと思ったんですけど、もう半分ウトウトしていたんで、頬っぺをパンパンってやって「やるかやらないかお前が決めろ」って言ったら、「やる」って言う。本当にあれはギリギリでしたけど、厳しい合宿の経験があって、自分の中で行けると思ったって言うんですよ。やっぱり自然体験は大事だと思うんです。
――現場である意味痛い思いもすれば、いやでも考えて学んでいく。その場をどう作るかということですね。
野口健氏:
痛いのもそうだし、あとは純粋に楽しいところもあるんですよね。やっぱり森の中は楽しいんでしょうね。教室で喋っているときと、森の中で活動するときって、顔が全然違いますもん。公立学校の中でそれが増えていくと、大半の子が経験できるじゃないですか。
――改めて野口さんが考えるSDGsとは何でしょうか?
野口健氏:
大きなテーマを掲げるっていうのもいいんですけど、何かやってみる。ひとつやるとその活動からこうしてみようかとかああしてみようというのがまた見えてきて、そっちに行くじゃないですか。その積み重ねだと思うんです。やっぱり住んでいる街がすごく大事だと思っていて。身近なところから具体的に何かアクションをしていくっていう方が、何か壮大な目標を掲げるよりもいいんじゃないかなと思うんです。
(BS-TBS「Style2030賢者が映す未来」2024年5月19日放送より)