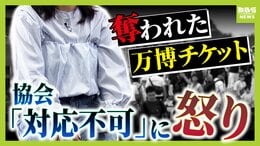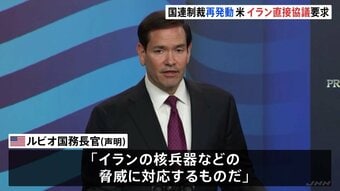「司法取引」と保護観察機関の「レポート」どちらを重要視?

萩谷麻衣子さん:
検察官との間で行われる司法取引と、保護観察機関によるレポートの内容というのはどういった比重の関係になってくるのでしょうか?
鈴木淳司さん:
水原氏に保護観察官が必ず1人あてがわれ、その人が司法取引書類の内容を確認し、こういう合意がなされていることも考慮に入れた上でレポートを書きます。
なので、どちらかというと司法取引は尊重するが最終的には保護観察機関の意見という形で出されていくので、保護観察機関の比重は重いと思います。

井上キャスター:
保護観察機関に対して、検察側・弁護側がアプローチすることはできない、という認識でいいんでしょうか。また、レポートは罪を重くするほうに作用するのか、軽くする方に作用が行きがちなのか、一般論として言えることがあればそのあたりを教えてください。
鈴木淳司さん:
基本的に弁護士がついて、保護観察官に会うということもします。なので弁護士がそこに同席することはありますが、黙秘権がない状態なので基本的には「本人が何を喋るか」というのが前提になります。
そして、レポートが出てきた段階で、弁護人が何らかの異議を申し立てることもするし、検察官も何らかの異議を申し立てることもしますが、基本的には「双方の意見を汲んだ上で、最終的なものは保護観察局が作る」という流れになります。
<プロフィール>
鈴木淳司さん
アメリカ・カリフォルニア州弁護士
30年近くアメリカで商事・刑事等の裁判を多数経験
マーシャル・鈴木総合法律グループに所属