「社会全体で検証するための情報を」
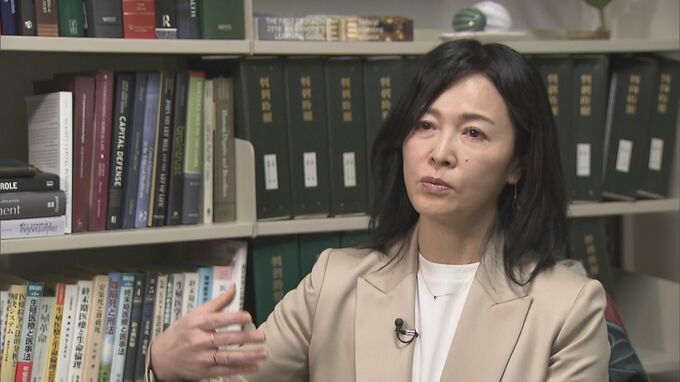
Q.今回の裁判の判決や進展が影響する可能性も含め、日本で死刑執行の告知のあり方が変わっていく可能性は、現実的にありますか…?
「 “変わっていくべき” だと思いますね。やはり民主主義社会で、死刑制度の下でだれか一人の命を奪うのであれば、どんな手続きを取っているかを、みんなで検証できるようになっていなくてはいけない。告知のあり方が変わるべきかどうかを、みんなで考えるための情報が、まずは広く明らかになることが大切だと思います」
「とりあえず現在の状態を教えてと。『なぜそういう運用になっているの』『他の国は違うのに、なんで日本はずっとそうしているの?』『その運用によってどんないい点と悪い点があるの?』全部とりあえず出してほしいと。情報を出してくれたら、社会全体で考えるし、もしかしたら現行の運用でいいとなるかもしれない。国が主張したように『そもそも伝える必要なんかないんだ、いきなり刑場に連行して執行しても別に問題はない』という答えが出るかもしれない。いずれにせよ、しっかり考える材料が欲しいという議論はあってほしいなと思いますね」
*******
死刑囚は生命犯であり、何の “告知” もなく、突然理不尽に命を絶たれた被害者の無念や遺族の悲しみに、寄り添わなければならないのは言うまでもありません。一方で、死刑囚の人権や尊厳は踏みにじっていいという考え方が正当であるとも、言い難いのではないでしょうか。
究極の刑罰の「告知」をめぐり、裁判所はどんな判断を下すのか。判決は4月15日午後に、大阪地裁で言い渡されます。
追記)判決は “死刑囚側が敗訴”

大阪地裁(横田典子裁判長)は4月15日の判決で、
▽現在の運用に基づく執行を受忍する義務がない点を確認することは、死刑執行を許さない効果(=確定した刑事判決との矛盾)を生じさせるものにほかならず、不適法だ。
▽賠償請求も、実質的には確定判決そのものの違法性などを主張するものにほかならず、判決の結果を無意味にすることを求めるもので許されない。
と断じました。
加えて、
▽「適正手続の保障」をめぐる主張についても、死刑制度は執行方法を含め、憲法31条に違反しないという判例が確立されている
▽「国際人権規約に反している」という主張についても、自由権規約委員会の意見は法的拘束力を有するものではない
▽執行前日に告知を受けた死刑囚が自殺した事案があったという経緯や、死刑囚の心情の安定への配慮などを踏まえれば、当日告知は一定の合理性を有すると認められる
などと指摘。
結果的に ▽受忍義務がないことの確認の請求は「却下」 ▽慰謝料2200万円の賠償請求は「棄却」するという形で、死刑囚側の訴えを全面的に退け、“当日告知は合憲”という判断を下しました。
(MBS大阪司法担当 松本陸)














