「適正に執行されているか “疑う” 機会少ない」「執行までの期間は刑罰ではないはず」
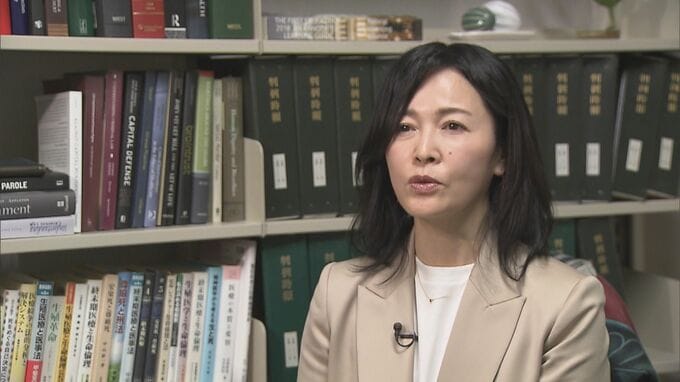
記者)Q.アメリカでは、死刑執行までのプロセスを定めたマニュアルに一般の人もアクセスできる状況がある一方、日本はそうした ”オープン” な状況にはなっていません。こうした違いが生じている背景には何がありますか?
古川原教授)「アメリカの場合、死刑執行にメディアが立ち会うことも一般的なので、“許されるようなやり方” で人の命を奪っているということを、みんなできちんと確認しようという考え方があると思います。日本の場合はまず、適正に死刑が執行されているかを “疑う” 機会が少ないのかなと思います。知りたくない人も多いとは想像できますが、国が情報を出さないことが許され続けてきたという点があると思います」
Q.国は当日告知の理由を「心情の安定を害さないようにするため」と説明しています。
「早めに教えると、本人がすごく動揺して、もしかしたら自死するかもしれない、刑務官に暴力を振るうかもしれない、他の死刑囚が動揺するかもしれないといった、いろいろな “不安” を想定しているのだと考えられます。ただ公式に掲げている『告知を受けた死刑囚が、穏やかでいられないからだ』という理由、知らせてほしい死刑囚もいるのに、『いやいや、あなたが落ち込むから教えませんよ』というのは、ある意味非常に “おせっかい” ですよね。パターナリズムという形で、押しつけがあると思います」
「そもそも死刑は、命を奪うという刑罰なので、執行までの期間は刑罰ではないわけですよね。その期間にたくさん苦しめようとか、なるべく死刑囚がつらくなるように処遇しようとか、そういう考え方は刑罰のあり方からすれば少し違うのではないかと」

Q.国は「執行までの期間に苦しめているわけではない」という姿勢だと思われますが、現状をどう捉えていますか?
「ちゃんと執行するためにやむを得ず拘禁しているという状況なのだから、執行までの期間は、丁寧に死刑囚を人間として扱おうという考え方もあっていいと思うんです。しかし、“執行までもなるべく、同じ社会のメンバーとして扱わないようにしよう” という考え方がかなり根付いて、疑問視しない風潮ができていると感じることがあります」














