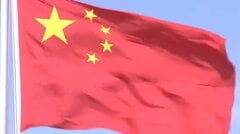国・大阪府から救いの手は?
小川キャスター:
国家プロジェクトということで、安心して請け負った方たちもいらっしゃったと思います。具体的に国や自治体はどういった手を打てるのでしょうか。

清水貴太記者:
一つ参考になるのは、新型コロナの際に事業者向けの貸付制度が国や自治体で設けられました。こうした事業者を救済するための法令を作る、ある種の政治判断ですね。こうしたことで、政治の力で何とか中小の事業者を救う手立てを考えていく必要があると思います。
東京大学准教授 斎藤幸平さん:
もっと強いことはできないのでしょうか。これから入札できないよう出禁にするとか、それぐらいの罰則も含めてやらないと、本当にこんなに頑張った中小企業の方たちが報われないですよね。
清水貴太記者:
一つ策としては、建設業法に基づく規制というところが考えられます。国や都道府県というのが、建設業許可を出しています。つまり建設を営んでいる方々への規制の権限を持っているわけです。
例えば一定の場合に、業者に対して建設業法に基づく規制をかけることができるのは、国や都道府県であったりするので、建設業法を生かして指導や勧告をすることによって、トラブルが考えられるような企業が、日本の工事に入らないようにするプランも考えられます。
東京大学准教授 斎藤幸平さん:
国交省や国がもっと動こうと思えば、そうした余地もあるということですね。
藤森キャスター:
建設の問題を論じてきましたが、そういう動きで近々に考えなければいけないのは、解体が始まっており、解体業者とも今後トラブルがあるかもしれませんよね。

清水貴太記者:
実は解体の方が、より切羽詰まっているという状況です。この未払いの問題が明るみに出たことにより、パビリオンの解体をしようと考えていた業者が、少し二の足を踏む状況が続いています。
解体は、建物を取り壊してしまうと、担保に残るものが何もありません。建設の段階だと、建てた建物を担保にして、金額の交渉ができます。ただ、解体は全部壊してしまうので、担保がありません。解体をしてから、未払いのトラブルに巻き込まれると、食いっぱぐれるリスクが非常に高まるというところで、解体の業者はそこを非常に懸念しています。
東京大学准教授 斎藤幸平さん:
このままレガシーとして残ってしまう可能性もあるということですか。
清水貴太記者:
ただ、博覧会協会は、土地を大阪市から借りている状態なので、いずれ敷地を返さないといけません。敷地を返すというのは、更地にして返さないといけない決まりになっているので、海外パビリオンも、大阪市が「これは残していいですよ」と言わない限りは、更地にして返さなければいけません。
レガシーに繋がるんじゃないかというところもありますが、そこはまた法律や大阪市と博覧会協会の関係性というところで、難しい問題も出てきます。
小川キャスター:
現在進行形の問題だということですよね。万博問題は全く終わっていないということです。
==========
<プロフィール>
清水貴太
MBS記者 誘致段階から大阪・関西万博を取材
元大阪府政キャップ
斎藤幸平さん
東京大学准教授 専門は経済・社会思想
著書『人新世の「資本論」』