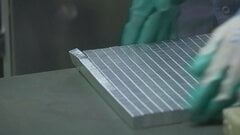(ブルームバーグ):物価変動を反映させた実質賃金は9月に、9カ月連続で前年を下回った。春闘での高水準の賃上げを反映して基本給は増加基調にあるものの、物価の上昇に追いつかない状況が続いている。
厚生労働省が6日発表した毎月勤労統計調査(速報)によると、持ち家の帰属家賃を除く消費者物価指数(CPI)で算出した実質賃金は前年同月比1.4%減。市場予想は1.5%減だった。CPI総合で算出したベースでは1.0%減と2カ月連続のマイナスとなった。
名目賃金に相当する1人当たりの現金給与総額は1.9%増と、前月から伸びが加速した。プラスは45カ月連続。基本給に当たる所定内給与は1.9%増と横ばいだった。
連合は先月23日に発表した2026年春闘の基本構想で、3年連続5%以上の賃上げを求める方針を示すとともに、実質賃金を「1%上昇軌道」に乗せることの重要性を強調した。物価高の影響で生活の向上を実感しにくい状況が続く中、賃金上昇の持続性のみならず、実質賃金のプラス転換・定着が引き続き焦点となる。
日本総合研究所の藤本一輝研究員は、賃金動向について、サンプル替えの影響もあり「数字としては弱い印象を持ってしまう」と語った。今後はガソリン減税などの影響でインフレが鈍化するとみており、実質賃金がプラスに転換するのは「12月ごろ」とみる。

政府が6月に閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針2025」(骨太の方針)では、29年度までの5年間で、物価上昇を1%程度上回る賃金上昇をノルム(社会通念)として定着させるという目標を掲げている。
高市早苗首相は物価高対策を政権の最優先課題に位置づける。5日の国会では、前日に設置した日本成長戦略本部で、物価上昇を上回る賃上げが継続する環境整備に向けた戦略策定を、賃上げ環境整備担当を兼務する城内実経済財政相に指示したと語った。今後は政労使の意見交換を行い、賃上げ機運の醸成に取り組む考えも示した。
賃上げのモメンタム(勢い)は追加利上げ時期を探る日本銀行にとって重要な判断材料だ。植田和男総裁は10月の金融政策決定会合後の会見で、経済・物価の見通しの実現確度は徐々に高まっていると指摘。春闘については、妥結状況の結果を待つということではなく、初動のモメンタム確認に「もう少し情報を集めたい」と述べた。
S&Pグローバルマーケットインテリジェンスの田口はるみ主席エコノミストは、賃上げについてはここ1、2年の強い動きが「少し緩慢になってきている」と指摘。ただ、賃金動向は日銀に利上げを足止めさせるほど「弱く転じてきているということではない」との見方を示した。
日銀は、新たな経済・物価情勢の展望(展望リポート)で、賃金と物価が相互に参照しながら緩やかに上昇していくメカニズムは維持されると指摘。人手不足感が強まる下で名目賃金は伸び率を高めていくとの見通しを示している。
佐藤啓官房副長官は6日の会見で、「賃金上昇を伴った持続的・安定的な物価上昇の実現は道半ば」と指摘。政府は責任ある積極財政の考え方の下、「物価高をさらに加速させないよう、戦略的に財政出動を行っていく」と語った。日銀に対しては、2%物価目標の実現に向けて引き続き適切な金融政策運営を期待すると述べた。
日銀は10月会合で政策金利を0.5%程度に据え置くことを7対2の賛成多数で決めた。ブルームバーグがエコノミスト50人を対象に同会合前に実施した調査によれば、次回利上げ時期について12月が50%、来年1月までは98%とほぼ全員が想定した。
他のポイント
- 実質賃金の算出に用いる消費者物価指数は、持ち家の帰属家賃を除くCPIが3.4%上昇、総合は2.9%上昇
- エコノミストが賃金の基調を把握する上で注目するサンプル替えの影響を受けにくい共通事業所ベースでは、名目賃金は2.4%増-前月1.9%増
- 所定内給与は、全体、一般労働者いずれも2.2%増
(11段落目に佐藤官房副長官の会見内容を追加して更新しました)
--取材協力:横山恵利香、下土井京子.もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp
©2025 Bloomberg L.P.