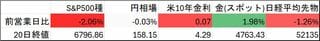(ブルームバーグ):SBI新生銀行が非上場化した際、株式の公開買い付け(TOB)に応募しなかった株主から強制的に株を買い取った際の価格が低過ぎるとして、ヘッジファンドなど海外投資家らが公正価格の決定を求めて東京地裁に申し立てを行っていたことが分かった。
ブルームバーグが確認した申立書によると、この申し立ては2023年11月に行われた。SBIホールディングスがSBI新生銀行を1株当たり2800円で非公開化した直後に当たる。申立人は、米シタデルやノルウェー銀行、ヘッジファンドのアトス・キャピタル、メイブン・インベストメント・パートナーズなどを含む旧株主だ。
会社法は、非公開化などの組織再編に反対した株主が公正な価格での買い取りを会社側に求めることができると定めている。「株式買い取り請求権」といわれ、株主は裁判所に公正な価格の判断を求めることもできる。

地裁が公正価格の判断を下すまでには、さらに1-2年かかる可能性がある。当事者が抗告すればさらに長期化する。裁判所が1株当たり2800円の買い取り価格を不当と判断した場合、SBI新生銀行は裁判所が認定した公正価格との差額の支払いを命じられ、その額は数十億円以上となる可能性もある。非公開化後、過去2年間でのSBI新生銀行の株式を巡る取引では、1株当たり3750円と7500円に相当する評価が付いた。
SBI新生銀行、ノルウェー銀行、アトスはそれぞれコメントを控えた。SBIやシタデル、メイブンからの回答は得られていない。
ブルームバーグは先月、SBI新生銀行が早ければ今月にも新規株式公開(IPO)の詳細について発表すると事情に詳しい複数の関係者の話を基に報じた。上場時期は12月中旬で、少なくとも1兆円を超える時価総額を目指しているという。今年最大規模のIPOとなる可能性がある。
高まる注目
公正価格を求める動きを巡っては、20年に伊藤忠商事が実施した子会社ファミリーマートを完全子会化するためのTOBに関連し、アクティビスト系ヘッジファンドのRMBキャピタル(現キュリRMBキャピタル)とオアシス・マネジメントが同様の申し立てを行った。東京地裁は23年、買い取り価格が低過ぎると判断したことで株式買い取り請求権に対する注目が高まった。
海外のヘッジファンドやアクティビストは、日本企業への投資を強化している。投資家からの企業価値向上への要請が強まる中、非公開化案件も増えており、株主に対して企業に説明責任を果たさせる手段として同請求権は注目を集めている。6月に発表されたトヨタ自動車などによる総額4兆7000億円に上る豊田自動織機の買収案件でも、海外投資家などからTOB価格に対する不満の声が上がっている。
SBI新生銀行の前身である日本長期信用銀行は、国内の金融危機が頂点に達した1998年に国有化された。その後、リップルウッド・ホールディングスや米資産家のJ・クリストファー・フラワーズ氏ら外国人投資家に売却され、2000年に新生銀行と改称し、04年に上場した。
21年にSBIが新生銀行の株式の約50%を取得し、実質的な支配権を獲得した。SBIは23年に政府が保有する2割強を除いた残り全ての株式取得を目指し、当時の株価に12.6%のプレミアムを乗せた1株当たり2800円でTOBを実施した。TOBに応じなかった株主からも、同価格でスクイーズアウト(強制買い取り)の措置を取った。
当時、SBI新生銀行は3500億円の公的資金を抱えていたが、上場したままでは株価を7500円にまで引き上げないと同金額を返済できないスキームだった。大幅な株価上昇は難しいとして、非公開化に踏み切った。
SBIの当時の開示資料によると、TOB価格を巡りSBI新生銀行の社外取締役らで構成される特別委員会は、1株当たり3000円を下回る水準では少数株主利益に配慮した結果であると結論付けることは難しいなどとの見解を示していた。
非上場化したSBI新生銀行は今年7月末に公的資金を完済した。同月に東京証券取引所に上場申請を行っていた。
--取材協力:Bei Hu、鈴木英樹.
もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp
©2025 Bloomberg L.P.