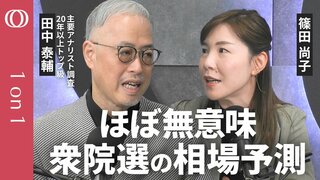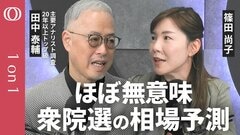(ブルームバーグ):高市早苗首相は24日、衆院本会議の所信表明演説で、関連経費を含めた防衛費を2025年度中に対国内総生産(GDP)比2%とする方針を明らかにした。従来計画の27年度から2年前倒しで増額する。
高市首相は近年、「新しい戦い方の顕在化など、さまざまな安全保障環境の変化も見られる」とし、「主体的に防衛力の抜本的強化を進めることが必要だ」と述べた。国家安全保障戦略で定める「対GDP比2%水準」について「補正予算と合わせて、今年度中に前倒して措置を講じる」と明言した。
高市首相は21日の初閣議で策定を指示した総合経済対策の3本柱に、物価高対応や危機管理・成長投資に加え、防衛・外交力の強化を据えた。トランプ米政権が同盟国に対して防衛費増額を求める中、日本が主体的に自国の防衛を強化する姿勢を示した形だ。
トランプ氏は27日から29日の日程で訪日する予定で、高市首相は21日の就任会見で、「日本自体の防衛力はしっかりと充実させていく」とトランプ氏に伝えたいと述べていた。
対GDP比2%目標は岸田文雄政権下の22年12月に策定した「国家安全保障戦略」に盛り込まれている。25年度当初予算の防衛関連費は約9兆9000億円で、同戦略が策定された22年のGDPと比べると1.8%だった。高市氏は今後策定する補正予算と合わせて2%となるよう措置を講じる考えで、1兆超が必要だ。
同戦略をはじめとする防衛3文書については26年中の改定を目指し、検討を開始することも改めて表明した。国家安保戦略は「おおむね10年」を念頭に策定したが、安全保障環境などに重要な変化が見込まれる場合には「必要な修正を行う」としている。
北大西洋条約機構(NATO)諸国は米政権の要求に呼応する形で、GDP比5%相当を国防関連費として拠出する目標で合意。ヘグセス国防長官は5月末、日本を含めたアジアの同盟国に対しても、対GDP比5%に向け引き上げるよう、シンガポールでの演説で要求していた。
積極財政
財政運営を巡っては、「強い経済」を構築するため戦略的に財政出動を行うと述べた。この過程で「成長率の範囲内に債務残高の伸び率を抑え、政府債務残高の対GDP比を引き下げて行くことで、財政の持続可能性を実現し、マーケットからの信認を確保する」と述べた。
現在、政府が財政健全化の指標として用いる「基礎的財政収支(プライマリーバランス、PB)」の黒字化には言及しなかった。今年6月に石破茂政権がまとめた「骨太方針2025」では25-26年度を通じてPB黒字化させる目標を示した上で、コロナ禍前の水準に向けて債務残高対GDP比の安定的な引き下げを目指すとしていた。
単年度ベースで経費と税収のバランスを計るPBと異なり、政府債務残高対GDP比は経済規模と比較して財政健全化を図る指標だ。中長期的な観点から柔軟な財政運営が可能となる一方で、単年度ベースの赤字が許容されやすくなる。政府債務残高の対GDP比は、債務残高の伸び率が成長率を上回らなければ、引き下げることができる。
高市氏は総裁選期間中、「純債務残高」の対国内総生産(GDP)比が緩やかに低下する財政運営を目指すとしていた。純債務残高は債務残高から政府保有の金融資産を差し引いたもので、さらに柔軟な財政支出を可能とする。
財務相に就任した片山さつき氏も22日、財政健全化への取り組みは、純債務残高対GDP比引き下げで「論理的には十分ではないか」との考えを示していた。
物価高対策
最優先課題と位置付ける物価高対策では、現金給付は行わないと改めて表明。ガソリン税の暫定税率廃止法案は臨時国会で成立させ、軽油引取税の暫定税率も早期の廃止を目指すとした。経営が厳しい医療機関や介護施設を補助金で支援する。
所得税が発生する「年収の壁」はこれまでの政党間協議を踏まえ、年末調整では最大160万円までとする規定方針で対応すると指摘。さらに引き上げる税制措置についても「真摯(しんし)に議論する」とした。
成長戦略の肝はリスクや社会課題に先手を打つ「危機管理投資」だとし、人工知能(AI)・半導体、造船、量子、バイオ、航空・宇宙、サイバーセキュリティーなどの戦略分野に対して、大胆な投資促進や国際展開支援、人材育成を含む総合支援策を講ずると重ねて強調した。「世界で最もAIを開発・活用しやすい国」を目指すとした。
社会保障制度改革に向けては、与野党と有識者を交えた国民会議を設置する方針を明らかにした。「給付付き税額控除の制度設計を含めた税と社会保障の一体改革について議論する」と述べた。
その他の発言
- 経済の強い成長に向け「日本成長戦略会議」を立ち上げる
- 5年間の「農業構造転換集中対策期間」で別枠予算を確保
- 原子力やペロブスカイト太陽電池含む国産エネルギーは重要
- 「地域未来戦略」で地方に大規模投資を呼び込み、産業クラスターを形成
- 外国人に既存ルールの順守を求め、土地取得のルールの在り方について検討
(高市首相の発言を追加し、更新しました)
もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp
©2025 Bloomberg L.P.