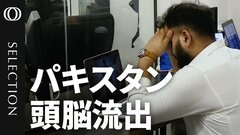(ブルームバーグ):トランプ米大統領の下で、世界は17世紀の重商主義に急速に回帰した。貿易はゼロサムであり、各国は自給自足を目指し、輸出が輸入を大幅に上回るべきだという考え方だ。
ルイ14世時代のフランスや欧州の絶対王制国家が実践したこの手法が「米国第一」主義の下で再導入され、米国が勝者となることを狙っている。
アダム・スミスはこの重商主義に対抗する形で自由市場の理論を打ち立てた。オックスフォード大学中国センターのジョージ・マグナス氏によれば、スミスは「重商主義が金銀の獲得に重点を置き、輸入抑制と輸出奨励を進めることは、市民の富の蓄積とは両立しない」と見なしていた。
スミスの思想は、20世紀の大半において西側で主流となったリベラリズムの基盤だった。
だが、トランプ氏は今年4月2日を「解放の日」と銘打ち、大がかりな高関税措置を発表。その狙いは、スミスが反発した世界を呼び戻すことだった。
市場は動揺したが、トランプ関税はその後も維持され、インドやブラジルといった重要な国に対してむしろ引き上げられた。驚くべきことに、ほとんどの国が報復せず、米国に極端に有利な貿易条件を受け入れている。
現時点では、米国第一主義の圧倒的勝利に見える。しかし重要な点がある。すでに数十年にわたり重商主義を実践し、その技術にたけ、むしろ一歩先んじているように見える国が存在する。中国だ。
中国の重商主義1.0-人為的な通貨安とWTOの抜け穴
マグナス氏は米国について、2000年代半ば以降に中国が切り開いた道に遅れて反応しているとみる。中国は01年末に世界貿易機関(WTO)に加盟したが、その中国を抑制する力が自らにはないことにWTOはすぐ気付いたという。
中国共産党が仕掛けた産業政策のいわば「長征」は、国有企業の特権や補助金、直接融資、優遇貸し付け、政府主導の信用供与、技術移転や調達政策など広範に及び、中国を「非市場経済」にとどめた。
その結果はよく知られた通りだ。米国で産業空洞化が進み、深刻な社会問題を引き起こし、最終的にトランプ氏のホワイトハウス入りにつながった。
中国は安価な製品から徐々に撤退し、ベトナムやバングラデシュなどの新興国にそうした製品の製造を譲った。15年の拙速な人民元切り下げは世界的な金融危機の懸念を引き起こし、貿易黒字は15-18年に6000億ドルから4000億ドル未満へと40%以上縮小した。
それでも中国は巧みに重商主義を続け、18年以降は米国の関税をものともせず貿易黒字を3倍に拡大し、現在は1兆2000億ドル(約179兆円)弱と過去最高水準にある。
中国の重商主義2.0-世界中にデフレ輸出
中国の対米輸出には57%という極端な関税が課されており、3年前のピークから約4分の1減った。それでも今年の全世界への輸出総額は過去最高を記録している。
米国の新重商主義への対応策は、他国が太刀打ちできない価格で世界中に輸出する、いわゆる「ダンピング(不当廉売)」だ。
中国は従来、デフレを輸出していると非難されてきた。米国が輸入する安価な中国製品は、米経済を非常にホットにしながらもインフレは抑えた。
だが中国は今や「内巻」を輸出している。つまり、過剰競争と供給過剰だ。採算割れの製品を世界市場に放出する処理法であり、中国はこれを実に効果的に行っている。
中国の対米輸出はWTO加盟後20年間の大部分において、世界全体への輸出とほぼペースで増えた。しかし新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)とトランプ政権1期目の関税導入、さらにバイデン政権がトランプ関税を継続したことにより状況は一変した。
キャピタル・エコノミクスのチーフエコノミスト、ニール・シアリング氏は、現在の貿易再編の最大要因はワシントンではなく北京にあると指摘する。
トランプ政権1期目に、中国はベトナムやメキシコを経由して対米輸出を迂回(うかい)したが、われわれの推計では今回はそうした動きは限定的だ。中国の対米輸出シェアは約4ポイント低下したものの、間接輸出は0.5ポイント増にとどまった。つまり、迂回輸出は落ち込み分の8分の1しか補えていない。
こうして中国は、ダンピング路線へ転換した。それは、トランプ政権2期目発足前から始まっていた。
中国政府が極めて厳格な新型コロナウイルス対策、いわゆる「ゼロコロナ」を2022年10月に解除して以降の12カ月で輸出価格は22%下落。他地域の輸出価格が横ばいの中で独り勝ちした。
中国の重商主義3.0-次世代産業の先行支配
重商主義は本来、後ろ向きの思想だ。製造業の雇用を米国に取り戻そうと、安価な輸入製品に高関税を課すトランプ氏のやり方はその典型例だ。
だが、中国の新重商主義は未来志向だ。ロングビュー・エコノミクスのクリス・ワトリング最高経営責任者(CEO、ロンドン在勤)は、中国が新興の成長分野で圧倒的な地位を築いていると指摘する。
国際エネルギー機関(IEA)によれば、中国は世界の電気自動車(EV)の70%以上、太陽電池の92%、ソーラーウエハーの98%、ソーラーパネルの85%を生産している。バッテリーも世界販売の4分の3超を占め、価格は3割近く下落した。
これらの分野は、中国国内で過当競争が激しく、価格下落と利益圧迫を招いている。中国政府は「反内巻」キャンペーンを展開。余った製品の行き先は、再び世界市場となっている。こうした輸出が、関連セクターでの中国のグローバル支配を固める可能性がある。
一方、トランプ政権下の米国は再生可能エネルギーを「詐欺」と見なし、化石燃料への依存を続ける。だが脱炭素が進めば、米国は重商主義の大敗を喫する恐れがある。ワトリング氏によると、中国の発電コストは今、米国の半分以下だ。
すでに重商主義が世界の潮流となっている。しかし米国はそのベストプレイヤーではない。最も経験豊富な重商主義者は中国であり、米国が構築しようとしている新たな秩序から最も利益を得るのは中国になる公算が大きい。
(ジョン・オーサーズ氏は市場担当のシニアエディターで、ブルームバーグ・オピニオンのコラムニストです。ブルームバーグ移籍前は英紙フィナンシャル・タイムズのチーフ市場コメンテーターを務めていました。このコラムの内容は、必ずしも編集部やブルームバーグ・エル・ピー、オーナーらの意見を反映するものではありません)
原題:Why America Will Lose Its Mercantilist Game: John Authers(抜粋)
コラムについてのコラムニストへの問い合わせ先:New York John Authers jauthers@bloomberg.netコラムについてのエディターへの問い合わせ先:Andreea Papuc apapuc1@bloomberg.netもっと読むにはこちら bloomberg.co.jp
©2025 Bloomberg L.P.